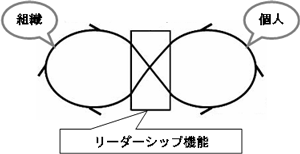| ■□■□ 第4章 ディレクション・マネジメント ■□■□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 管理職の仕事って何だ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本書を読まれている方々の、それぞれの会社内での地位や立場はさまざまにあるでしょう。部長職にいる人もいれば、課長職の人もいるし、役づきではない人もいることでしょう。はたしてみなさんは、自分の地位にみあった働きができているでしょうか。部長という地位にある人は、部長としての仕事がきちんとできているか、あるいは課長という地位にある人は、課長としての仕事がきちんとできているか。残念ながら、これまでのコンサルティングの経験からいえば、部長としての仕事ができない部長や、課長の仕事ができない課長が実際には非常に多いのが実態です。この章のテーマは、「部長としての、あるいは課長としての仕事がなぜできないのか」「どうすれば部長としての、課長としての仕事ができるようになるのか」です。 まず第1に、部長や課長といった中間管理職は何をするべき人たちなのかをあらためて考えてみる必要があるでしょう。というのも、中間管理職に対する風当たりが最近、厳しくなっているからです。たとえば、「これからの企業は、ピラミッド型からフラット型へと移行し、そうなれば管理職は不要となる」とか、「コンピュータによるネットワーク社会が構築されれば、必然的に管理職はいらなくなる」などと、未来型ビジネスを説く書が目につきます。財界の重鎮である、ダイエー会長の中内氏は「自分とパソコンとパートタイマーの人がいれば、ダイエーは動く」とまで言っています。(だからおかしくなった?!) 「部長職や課長職をなくせば、組織の風通しもよくなる」と考えている経営者も多いようです。それはまた、裏を返せば、組織の風通しが悪いのは部長や課長がいるからだと考えているということでもあります。しかし、パソコンによるネットワークをつくったとしても、それが部長や課長の代わりをできるでしょうか。部長や課長がいなくなることで、本当に組織内の風通しはよくなり、チームや組織の生産性はあがるのでしょうか。 組織のなかでの管理職の役割とは、「組織を構成する1人ひとりの個人と組織とをつなぐ接点となる」ことです。そしてそれは、トップダウンとボトムアップの調整機能を果たすことによって可能となるのです。その仕組みを図で表せば、次のようになります。
ですから、近未来の企業の形態がフラット型になろうと、従来通りのピラミッド型であろうと、中間管理職がいなくなろうと、組織と個人がトップダウンとボトムアップを繰り返しながら、目標や方針をつくりあげていくという仕組みに変わりはありませんし、それを可能にするために組織と個人との接点が必要となることにも変わりはないのです。 また、コミュニケーションの章で説明した通り、いかに情報通信機器が発達しようと、デジタル化できるものとできないものは必ず存在し続けると断言できます。デジタル化できないものを扱うことができるのは「人」だけです。その意味では、中間管理職という名称は消えるかもしれませんが、個人と組織をコネクトする役割の人はいかなる時代においても存在するはずなのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 メンバーの責任と権限を明確にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本書はグループワーク、あるいはチームワークをテーマとしていますが、そもそも仕事をするときになぜ、グループやチームを構成する必要があるのでしょうか。 答えは簡単です。1人でできる仕事とグループやチームでできる仕事とでは、その内容に大きな違いがあるからです。いい方を替えれば、1人ではできない仕事だから2人でやる、2人ではできない仕事だから3人でやる。これが、チームやグループ、あるいは組織や企業をつくる際の考え方です。 こんな当たり前のことをわざわざここで述べているのも、実はこの当たり前のことがよりよいチームワークづくりを考える際のカギとなってくるからです。「1人ではできない」のはなぜかという理由は次の2つのです。1つは、時間が足りないという理由。もう1つは、自分のもつ専門知識ではできないという理由です。1人でやるには時間が足りないから人手が欲しいのですし、自分の専門知識ではできないから自分にはない知識をもっている他の誰かを求めるのです。実際のビジネスの現場では、この2つの理由があいまって、チームやグループをつくる必要性が生まれてくるものですが、とりあえずここでは、チームやグループが時間と専門知識との2つのテーマのうえに成り立って「1人ではできない仕事だから2人でやる」というのは、チームや組織のレベルでも同様です。単独のチームではできない仕事を複数のチームが集まって協力して行なったり、あるいは異業種間や競合する同業他社が提携して1つの事業を行なうことも今や珍しいことではありません。やはり、時間と専門知識の2つの理由から、協力関係が成り立っているのです。
1人ひとりのメンバーが自分の責任と権限を明確に把握することが、チームとして仕事を進めていくための重要ポイントです。同時にこれは、目標通りの成果を達成できたかどうか、仕事を評価するときの重要ポイントでもあります。すでに説明したように、5つの経営資源(人、モノ、お金、情報、時間)のパワーバランスが崩れている現状で、責任と権限を5つの資源にどのように振り分け、かつ明確にしておくかが、この章のテーマであるディレクションにもかかわってきます。責任と権限が非常にあいまいになっている現状こそが、5つの資源を十分に生かせない事態をつくり出している最大の原因であることを理解しておいてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ディレクションする前に知っておくこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム、グループで仕事をするときに、個人と組織との接点となってトップダウンとボトムアップとの調整を行ない、またチーム内の役割分担(責任と権限)を調整するのがリーダーの仕事になるわけですが、それを可能にする方法がディレクションです。しかし、ディレクションをするためには、チームとしての行動計画が明確になっていなければなりませんし、また行動計画を立てるためには、チームの目標が設定されていなければなりません。つまり、目標と行動計画の設定こそ、効果的なディレクションをするための必要条件なのです。
具体的な行動計画を立てるためにはリーダーは、目標の設定以外にも、各メンバーの時間的な余裕(時間予算)と各メンバーの専門知識、あるいは業務処理スキルのレベルをきちんと把握しておくことが重要です。なぜなら、そもそもチームを組んで仕事をするのも、この2つの課題を克服するためなのですから。しかし現実には、この点を明確に把握できているリーダーは非常に少ないようです。それどころか、自分自身の時間予算を把握できている人すらあまりいないようです。 時間予算と専門知識・業務処理スキルは、どの仕事を誰にやってもらうのかという役割分担を決定するための基礎データとなるものですから、できれば社内のデータベースとして共有化されているのが理想です。みなさんは「スパイ大作戦」という昔のアメリカもののテレビドラマをご存じでしょうか。この番組では毎回、秘密の作戦指令を受けたスパイのリーダーがその都度、作戦遂行に適したメンバーを選ぶために、各メンバーの顔写真や名前のほか、「変装が得意」とか、「メカに強い」など、それぞれの得意分野・技術を記した資料を参考にするのですが、これはもう立派なデータベースです。現代のビジネスでもこのアイデアを生かし、たとえば社内に今あるパソコン・ネットワークやLANシステムで、社員1人ひとりの専門知識・業務処理スキル、あるいは現時点での時間予算といったデータを引き出せるように改良すれば、そのシステムは効果的なディレクションを実現するための理想的なシステムになるはずです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ディレクションのポイントとフォロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここまでは、ディレクションの準備についての話でしたが、次にディレクションするときに心がけるべきことについて説明しましょう。 まず第1のポイントは、仕事の5つの資源(人、モノ、お金、情報、時間)を整理してメンバーに伝えることです。チーム内の役割分担にしたがって、メンバーにそれぞれが担当する仕事を指示するときに、「その仕事にはどんな人間がかかわっているのか」「どういったモノ、コトなのか」「予算はどれくらいか」「どういう情報があり、どのくらいの時間でやらなければならないのか」、などを伝えなければなりません。このうちで1つでも欠けると、ディレクションを受けたメンバーがその仕事をうまく進めることができません。委任に関するハウツー本には「仕事の全体像を伝えること」といった解説がなされていますが、それは仕事の5つの資源を伝えることにほかなりません。 第2のポイントは、なぜその仕事をやるのかという動機(理由・目的)をメンバーに伝えなければならにということです。理由なり目的を相手に伝え、また相手と理解しあわなければなりませんが、そのためにはリーダー自身が、事前に自分なりの動機を明確にしておかなくてはなりません。しかし実際のところ、「社長命令だから」とか、「とにかく緊急の仕事だから」といった説明ですませてしまうリーダーが多いものです。これではディレクションを受けたメンバーのほうは、仕事の内容(質と量)が把握できてないため、自分なりの解釈で質と量を設定し、その結果としてリーダーの望んでいる成果をあげられないことにもなるのです。 第3のポイントとして、早めにディレクションすることです。時間が足りないからチームで仕事をしたり、あるいは部下に仕事を委任するのですから、投下時間が長いほど、委任された部下にとっても都合がよいでしょう。そして、投下時間を長くする方法とは、開始を早めることですし、そのためには早めにディレクションしなければなりません。 第4のポイントとしてあげたいのは、伝える内容は第2章で説明した7項目だということです。少なくとも投下時間と動機、優先順位だけは明確に伝えなければなりません。
しかし、仕事の進捗状況をチェックするだけでは、実はフォローが十分だとはいえないのです。仕事には事前にわかっている仕事、つまりすでに指示されている仕事のほかに、事前にわからない仕事があるからです。突発的に生じた仕事にどう対応するかは、優先順位にかかわる問題です。新しい仕事に優先的に取り組むべきなのか、あるいは従来の仕事を優先するか、そうしたフォローも必要なのです。 最後に、1つの仕事が終ったときには、その都度、仕事の結果を評価しなければなりません。どのくらいの時間がかかったか、それをデータベースに記録することで、次回の仕事の行動計画を立てる参考データとなります。また、専門知識、業務処理スキルが十分にあったかどうか、あるいは1つの仕事を経験したことで新たな専門知識・業務処理スキルが身についたかどうかというデータも同様です。さらに、目標が達成できたかどうかというデータも、次回の仕事で目標を設定するための参考データとなります。このように仕事の評価をすることで、より適切な目標と行動計画の設定が可能となります。それはリーダーのディレクションの能力がアップすることを意味しますし、そうなれば自動的にチーム全体の能力アップにもつながります。 リーダーにとってディレクションの有効性とは、リーダーシップが発揮できるというだけではありません。メンバーに仕事を委任することができれば、本来はリーダーみずからやらなくてもよい仕事なのにやらざるをえない、本来やるべき仕事に時間を投入できるようになります。さらにディレクションは、情報機器の活用次第で時間も手間も大いに省くことが可能なスキルですから、その活用法をマスターする意義は大きいでしょう。 ディレクションは部長が部長であるための、課長が課長であるための重要なスキルだといえるのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 リーダーシップを発揮させる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この節では、これまでに説明したディレクションのスキルについて再度、要点をまとめておきたいと思います。 リーダーシップを説くビジネス書には、「先見性とチームをまとめる能力があるかどうかが、リーダーシップを発揮できるかどうかのカギとなる」といった表現がされていますが、本書ではここまで、「ディレクションがうまくできるかどうかが、リーダーシップを発揮できるかどうかのカギとなる」という考えを説いていました。部長が部長としての仕事ができているかどうか、課長が課長としての仕事ができているかどうかは、部下に対して適切なディレクションを行なっているかどうかにかかってくるのです。 効果的なディレクションを行なうためには、チームの各メンバーの時間予算を把握しなければなりませんし、それができればチーム全体の時間予算を把握することもできます。さらに1ヵ月後、あるいは半年後、1年後のチームがどういう状態にあるかが把握でき、したがってこれから取り組もうとしているプロジェクトにどれくらいの時間を割くことができるのかが判断できます。また、メンバーの専門知識・業務処理スキルを把握できれば、どのメンバーにどんな仕事を割り振ればいいのかが判断できます。メンバーの力量を把握することは、チーム管理の基本です。 また、適切なディレクションをするためには、リーダーがプランニングとタイムマネジメントの能力を身につけていなければなりません。適切なフォローをするためには、事前にわからない仕事に対応し、時には仕事の分担や当初の指示を変更しなければなりませんから、それを判断するにはリーダーがアクションマネジメントの能力をマスターしていなければなりません。つまり、優れたチームリーダーとは、タイムマネジメント、プランニングマネジメント、アクションマネジメントの3つのセルフマネジメントの能力を身につけているリーダーのことをいうのです。そして、セルフマネジメントの能力を身につけるためには、まず仕事のOS(仕事の原理・原則)を理解しておかなければなりません。
交通整理をするだけなら、セルフマネジメントも必要ありません。部下が相談にきたときに、臨機応変にリアクションすればいいだけのことです。しかしリーダーシップをもつためにはプロアクション、つまり事前にアクションすることこそ重要で、それができるかでリーダーとしての力量が決まり、またチームの力量も決定づけられるのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ Yさんの情報共有化Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yさんチーム「拡販プロジェクト」にのぞむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M取締役からさんチームに人気商品Zのさらなる拡販の命が下されました。Yさんと相談のうえ、この「拡販プロジェクト」を題材にチームの情報共有化の具体策を模索することにしました。それで今回はM取締役、商品Zの開発担当部長であるM部長もまじえて、プロジェクトのブリーフィングが行なわれました。
全員、爆笑!! かくして「拡販プロジェクト」のリーダーはM取締役、サブリーダー、アドバイザーはM部長となり、各行動計画は各メンバーの責任で行なう役割分担が実現しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy Right (株)仕事の科学研究会