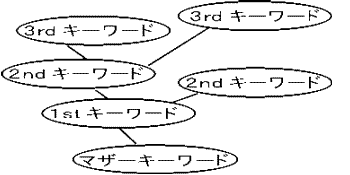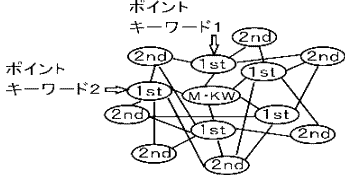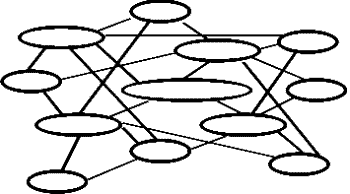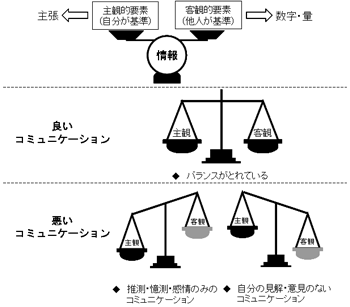| �r�W�l�X�R�~���j�P�[�V���������コ����A�ڏ��� | ||||||||||||||||||||||||
| ���������@��@�`���H�ҁ`�@�������� | ||||||||||||||||||||||||
| 1 �����̈ӌ����܂Ƃ߂� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�c�Ɖۂ̃t���A�̈�p�A���ۂ̃\�t�@�ł́A�ے��ƕ����̉ۈ��Ƃ��e�[�u��������Řb������ł���B2�l�Ƃ��A������Ȋ�����Ă���̂����\�\ �@�u�N����������イ�c�Ƃɍs���Ă���A����̌������ǂˁA�������A�������ƂɂȂ��Ă���ˁB�_���Ă��Ȃ����Ă����̂͒m���Ă邯�ǁA�N�̍l���͂ǂ��H�v �@�u�ꐶ��������Ă������Ȃ�ł����ǂˁA�Ȃ��Ȃ��c�c�B�������A�����Ȃ�ɁA���邱�Ƃ͑S������Ă����ł���B�v �@���������Ȃ���蒠����肾���A���܂ł̌o�܂��m�F���Ȃ���A�������n�߂��B �@�u2�������t�H���[���āA����6�������Ă邵�A���i�̐����͏ڂ����b���Ă�����肾���B�ł��A��������܂莞�Ԃ��Ƃ�Ȃ��āB������A���悤���Ȃ���ł���ˁBA������Z�����l�ł�����ˁc�B�������Ƃ����āAB����ɏЉ�ꂽ�l�ł�����ˁA������Ă邽�߂ɂ��A�ق��Ƃ��킯�ɂ������Ȃ����B�_�Ă��ꂽ��A���������ӂ���ɂȂ�Ǝv����ł���ˁB�����A������l�̘b�͎����X���Ă���Ă邵�B�����A�Ȃ��Ȃ��\�肪�v �@�u������Ƒ҂����v �@����Ăĉے����ۈ��𐧂����B �@�u�N�˂��A�����Y���Y���ƌ��t����ׂȂ��ŁA�����Ɛ������Ęb���Ă���Ȃ����Ȃ��B�������Ă��킩��Ȃ���B�N��A����̌��ɂ��āA�ǂ��v���Ă�́v �@�u�����݂͂���Ǝv����ł����A�ł��Ȃ��Ȃ���������b���ł��Ȃ��āA�l���������ꂪ�C�ɂȂ��Ăāc�v �@�u������ꌾ�ł����ǂ��ȂI�v �@������x�A�ۈ��𐧂����ے����A���x�͂����傫���Ȃ��Ă����B �@�u�ǂ����āA���́`�A�Z�����āA�Ȃ��Ȃ���Ȃ����Ă������c�c�A�ł��s�������ĉ���Ă���邵�A�����甃���Ă�������͂���Ǝv����ł����A�܂�������m���ł͂Ȃ����ǁA�ł��ӗ~���Ȃ�������A����Ă���Ȃ��ł��傤���B���`��A�ꌾ�Ō������Ă����Ă��v �@�u���ꂶ�Ⴀ�A�_��ɂȂ���|�C���g�͉��H�v �@�u�|�C���g�́c�A����ς�t�H���[�𑱂��āA���i�̐��������āc�v �@�u���Ⴀ�A������_��ł���H�v �@�u���܂ŁA2�������t�H���[���Ă�������A����1�����c�A����3������������Ȃ��ł����ǁv �@�u�N�˂��A��x���̒������Ă݂���ǂ������v �@�u�����A�ł����v �@�u�����A��������B�܂��N�̔]�݂�����U���Ă݂悤���B���ƃy���������āv �@�u�͂��c�c�v �@���̂��Ƃ��킩���A�Ƃ�����ʼnۈ��������L����ƁA���̒����ɉے���"�����q�`����"�Ƃ����L�[���[�h���ЂƂA�������B �@�u���āA���̃L�[���[�h���݂āA�^����ɘA�z���錾�t�͉����v �@�u���Z�A�ł����ˁv �@���x�́A���Z�Ƃ����L�[���[�h���������܂ꂽ�B �@�u���ꂶ�Ⴀ�C"���Z"�Ƃ����L�[���[�h����A�z���錾�t�́H�v �@�u�Ȃ��Ȃ��l�܂�Ȃ��A�ł��ˁv �@���炭2�l�ł���Ȃ������J��Ԃ��A�₪�Ď���ʂɃL�[���[�h���������܂ꂽ�Ƃ���ŁA�悤�₭�ے����������n�߂��B �@�u����̓u���C���E�}�b�v�Ƃ����ĂˁA�܂������Ă݂�ΌN�̔]�݂��̉�U�}����B���A�N�̓��̒��ɂ́A�����������L�[���[�h���×����Ă��āA���ꂪ��������Ă��Ȃ���ԂȂB��������Ă��Ȃ�����A�����ʼn_�ɃL�[���[�h����������o���Ă��邾���ŁA�ؓ��̒ʂ����b�������Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�킩�邩���v �@�u�Ȃ�قǁA�Ȃ�قǁv �@�u���Ⴀ���ɁA���̃L�[���[�h�����Ă݂��v �@�u�ǂ������ł����v �@�u"���Z"�Ƃ��A"�Ȃ��Ȃ��l�܂�Ȃ�""�\���b���Ȃ�"�Ƃ����̂́A�S�������悤�ȈӖ��������낤�B������Ȃ��Ȃ���Ȃ��Ƃ����L�[���[�h�ő�\����B�ŁA����Ȃ��L�[���[�h�������Ă��܂��B���ꂾ���ł������������肷�邾�낤�v �@�u�����ł��ˁB����Ȃ�A"���G���߂�"�Ƃ�"���@�s��"�Ȃ�Ă����̂́A"�w���ӗ~�s��"�Ƃ������ƂŁc�v �@�b������������ݍ��߂��ۈ��������Ő������Ă����̂��A�ے��͖��������ɒ��߂Ă��邾���\�\ �@�u�ے��A�ǂ����4�̃L�[���[�h�ɐ����ł��܂�����v �@�u�ŁA�N�͂�����݂āA�ǂ��v���B�ꌾ�ł����Ă݂��v �@�u�����ł��˂��B���낻�댋�_���o�������Ȃ��Ă������Ƃł��ˁv �@�u�ł�������Ȃ����B���ꂾ��A����B���낻�댋�_���o�������A���ꂪ�N�̍l������v �@���邢��ł��Ȃ����ۈ��Ɍ������āA�ے��������Ă������B �@�u�����A�ŏ�������Ȃ���������Ȃ����B�`����̌��ɂ��āA�ꌾ�ł����A�N�̍l���͂ǂ������v �@�u�ꌾ�ł����āA���낻�댋�_���o�������Ǝv���Ă��܂��B����Ƃ����̂��c�v
|
||||||||||||||||||||||||
| 2�@��ςƋq�ς����� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�ے��I�v �@�c�Ɖۂ̃f�X�N�����Ԓ�����A�ЂƂ�̉ۈ����f���ڋ��Ȑ��������ė����オ�����B �@�uA�㗝�X����̓d�b�Ȃ�ł����A���iB�̍w���҂���N���[���������������Ȃ�ł��v �@�����b���Ȃ���ے��ɋ߂Â��Ă����ۈ��́A�ے��̊��̖T��ɗ����Ȃ���A���n�߂��B �@�u�w���҂�C����Ƃ����l���G���C�����œd�b�������Ă��������ł��B���ł��A���iB�ɍ��{�I�Ȍ��ׂ�����炵���āA�i����Ƃ������Ă邻���ł��B�����Ȃ�Α��Q�����Ȃ�Ă����b�ɂȂ邩������܂���B���{�I�Ȍ��ׂȂ�A�㗝�X�̖��ł͂Ȃ��āA�E�`�̖��ł��ˁB�㗝�X�Ƀt�H���[�������Ȃ��āA����ς莄��C����Ƃ����l�ɓd�b�����Ă݂܂��傤���B����Ƃ��ے�����d�b�������Ă������������������ł��傤���B�ǂ����܂��傤�v �@�u�܂��A���������āv �@�ے��͑��̈֎q�ɍ���悤�A�d���ʼnۈ��Ɏ����Ă���A�q�˂��B �@�u�炵���Ƃ��A��������Ȃ��Ƃ������Ⴀ�A�d���ɂȂ���B���{�I�Ȍ��ׂ�����炵���Ƃ����̂́A�ǂ��������ƂȂB���iB���܂����������Ȃ��Ƃ������Ƃ����H����Ƃ��A�������ǁA�����Ƃ��������Ƃ��Ă���Ȃ��Ƃ������ƁH���̂��q����̎g������������Ȃ��́H�ǂ��Ȃ́v �@�u����A����́c�v �@�u���{�I�Ȍ��ׂ��Ƃ������̂͒N�H�㗝�X�Ȃ́H����Ƃ����q����Ȃ́H�v �@�u���q�����������Ă�Ǝv����ł����v �@�u�v�����āA���ꂶ�Ⴀ�����B���������A�����͉��Ȃ́B���{�I�Ȍ��ׂȂ̂��A�s�Ǖi�Ȃ̂��A���q����̊��Ⴂ�Ȃ̂��A���ꂪ�킩��Ȃ���A�Ή��̂��悤���Ȃ�����Ȃ����v �@�u�����A�܂��v �@�u�ŁA�㗝�X�̒N���A�����Ă����́v �@�uA�q����ł��v �@�u�㗝�X�̒N���A�ǂ������Ή��������́v �@�u�Ή������̂�A�q����炵�����ǁB�ޏ��A�Q�ĂĂ�����A������Ƃ����Ή������Ă��Ȃ���Ȃ����Ǝv���܂��v �@�u����͌N����������B�炵���Ƃ��A���Ǝv���Ƃ����̂͌N�̎�ς���B�܂��q�ϓI�Ȏ����ׂāA������n�b�L�������Ă����B���̎����ɂ��ƂÂ��������ŁA�N�̈ӌ������Ă���B������m��Ȃ���A�N�����ĉ��̑Ή����Ƃ�Ȃ����낤�v �@�u�킩��܂����B���ꂶ�Ⴀ�A�����v �@�}���Ŋ��ɖ߂��čs���ۈ��̌��p�����Ȃ���A���ߑ��̂ЂƂ��A���炵�Ă���悤�ȉے��̗l�q���B������10����\�\�B �@�����قǂ܂œd�b�ʼn����b������ł�����̉ۈ����A�K�v�ȏ�������ł����Ƃ݂��āA�ے��ɏΊ�������Ă����B �@�u�ے��A����c���ł��܂����v �@�u����ŁA�㗝�X�͂ǂ��N���[���ɑΉ������́v �@�u�Ή������̂�A�q����ł��B�ޏ��͓��Ђ�������̐V�l�ŁA���i�a�ɂ��Ă̒m���͂܂������Ȃ���ł���B������A���q����̘b���Ă��A���i�Ɍ��ׂ�����̂��A�g�����������̂��A�킩��Ȃ������ł��B���܂��ܒS���҂��S���A�O�o���ŁA����ō����ăE�`�ɘA�����Ă����Ƃ����킯�ł��B�Ƃ肠�������q����ɂ́A�S���҂ɘA��������Ɠ`�����Ƃ������Ƃł��v �@�u���q����͂ǂ����ē{�����v �@�uA�q����ɏ��iB�ɂ��Đq�˂Ă��������Ȃ����A��������Ј������Ȃ����Ă����āA�{�肾���������ł��v �@�u����Ⴀ�A�������낤�B�Ƃ���ŌN�A�������Ƃ͈���āA�����Ɨ��������Ă�ˁv �@�u�����B�������킩��A�Ή�������R�ƕ�����ł��܂�����ˁv �@�u�N�͂ǂ��������H�v �@�u�`�q����̘b�����ł́A�N���[���̌�����c���ł��܂���B�ʏ�Ȃ�A�܂��㗝�X�̒S���҂��炨�q����ɘA�����Ƃ��Ă�����āA���ׂȂ̂��A�s�ǂȂ̂��A�g�����̖��Ȃ̂��A�����f���Ă��炤�̂��A�܂��ؓ��Ȃ�ł����v �@�u���q����͓{���Ă�낤�v �@�u�����B������l����ƁA�Ƃɂ��������ق��������ł��傤�B�㗝�X�̂ق��ł́A�����ɂ͒S���҂ɘA�������Ȃ��Ƃ����Ă܂�����A�����͎��̕��ł����ɂ��q����ɃR���^�N�g���Ƃ��āA�b���Ă݂܂��B�㗝�X�ɂ́A���ƂŎ����������Ƃ��܂��v �@�u����A�������Ԏ����v �@�ے����A����܂łƂ͑�Ⴂ�ɁA�@���悭�Ȃ����B �@�u�����_�ł́A���ꂪ�ŗǂ̑Ή��Ǝv���ˁB�Ȃ��N�A �q�ϓI�Ȏ����ƁA��ϓI�Ȉӌ��A���ꂪ�d���Ƃ����Ԃ̗��ւ���v
|
||||||||||||||||||||||||
| 3�@���Ԃ�Z�k���� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�A�Ǝ��Ԍ�̌ߌ�6�������A�c�Ɖۂ̎Ј��̂����A���l�����Q�X�܁X�A�~�[�e�B���O���[���ւƏW�܂��Ă����B���������Ȃɂ��Ă���A����́A���ɏ����ꂽ"���q�l�͐_�l�ł�"�̕�����A�����ʊ�Œ��߂Ȃ���A�ׂɍ������Ј��Ƀu�c�u�c�Ƙb���|���Ă����B �@�uQC�T�[�N���Ȃ�Ă��������āA����A����A���ʘb�����肶��Ȃ����B�c�Ƒオ�o��킯�ł��Ȃ����Ȃ��A�����B�I���͑����A�肽����v �@�u�܂��A���������Ȃ�B������t���������v �@����������ׂ̎Ј��ɁC�`����͕s���C�Ȋ�������āA�Ȃ��������������B �@�u�������Ȃ��A����QC�T�[�N���́A���������c�Ƃ̌����A�b�v���e�[�}�Ȃ��B�����A�b�v�ǂ��납�A����Ȃ̎��Ԃ̖��ʌ����ł����Ȃ�����Ȃ��B�����������̃T�[�N���̈��̂����āA"���q�l�͐_�l�ł�"�Ȃ�Ă��A�Ȃ��悭�킩��Ȃ������v �@�u�݂�ȑ������悤������A���낻��n�߂悤���v �@�c�����̎Ј��̐������}�ɁA����܂ł̕����̂��������Ō��킳��Ă�����b�����f�����B �@�u�����̋c��͌��́A���_�̗Ƃ������Ƃł����A�����̂悤�Ɏ��R���_�Ƃ��܂��傤�v �@�悤�₭�n�܂���QC�T�[�N���̉�����A���Ԃ��o�ɂ�AA����̊�̉Ղ����\��[���Ȃ��Ă���悤�������B������ ���_�̗l�q���A���ԂƂƂ��Ƀ_���Ă����B �@�u���ǂ����A���͂Ƃ��ẮA�s�i�C���������Ƃ���ȁB�ȑO�͂����A��э��݂ł����\�A�_��Ƃꂽ����ˁv �@�u�������Ȃ��A��Ԃ悩�����̂�3�N�O���炢���Ȃ��v �@�u����A4�`5�N�O���낤�B���̍��͂����A�V�������i���ł邽�тɕK���_�Ă���邨���ӂ���������Ȃ��v �@�u���������B�p���t���b�g�������Ă����āA�w�ǂ����x���Ă��������Ō_��Ƃꂽ�肵�Ăˁv �@�u���������A���̍��͌o������\�g�������ˁv �@�u������Ƒ҂��Ă����v �@����܂Ŗق��ĕ����Ă��邾��������A���������A���܂肩�˂��悤�Ɍ����J�����B �@�u4�`5�N�O�͂ǂ��������Ƃ��A�p���t���b�g�����Ō_�Ƃꂽ�Ƃ��A�����̋c��̌��͂ɊW�Ȃ��b���肶��Ȃ����B����Ȃ��Ƃ�����_���_���Ƃ���Ă��邩��A�������Ԃ��������B�����͂����A��߂悤��B���ʂ���A����Ȃ��Ɓv �@�u��߂���Ă������āA�܂����_�͂łĂȂ���v �@�u����Ȃ��Ƃ���ĂĂ��A���_�Ȃ�ďo��킯�Ȃ���B�I���͂����A���v �@�c�����̎Ј����Ȃ��߂�̂��������AA����͂��łɋA��x�x���n�߂Ă����B �@�u�܂��҂��Ȃ�AA�N�v �@�h�A�̌��������畷���������ɔ������āA�����o�[�S�������������ƁA���傤�ǃh�A���J���ă~�[�e�B���O���[���ɓ����Ă���ے��̎p���������B �@�uA�N�̌������Ƃ������Ƃ�����B���̃T�[�N���͂������Ԃ���������l�q�����ɗ������ǂˁA�Ȃ�قǁA�Ȃ�قǁv �@���Ȃ����Ȃ���A���֎q�ɍ������ے��͘b�𑱂����B �@�u�����Ԃ̉�c�Ƃ����̂́A�m���ɔ�����̂����A���܂蓾��Ƃ��낪�Ȃ��I����Ă��܂����B�N�����̘b���Ă���ƁA�ǂ������ʘb�������悤���ˁB�������낤�AA����v �@�u�����ł���v �@�u�����Ă݂�A�E����c���ȁB�b�����Ă��邤���ɁA���e���{���̃e�[�}����ǂ�ǂ�Ă����Ă��܂��ȁB���̂����A�S�R�W�Ȃ����Ƃ�b���Ă���Ă킯���낤�B�����炳�A�b�����e���A�c��A�ړI�ɍi���Ăق����ȁB��������Ύ��Ԃ̒Z�k�ɂ��Ȃ�B����������c�ɂ���ɂ͂ǂ������炢���̂��A�ǂ������H�v���K�v�Ȃ̂��B�����������l���Ă݂悤��B�ǂ������A�c���v �@�u�����ł��ˁA���܂��傤���v �@�������ĉے��̒�Ăɂ��A"���q�l�͐_�l�ł�"�̍����̃e�[�}�́u��̎��ԒZ�k�̂��߂̍H�v�v�ɕύX����\�\ �@������30����A�~�[�e�B���O���[���ł́A����A���傫�Ȑ���グ�Ă����B �@�u���ꂾ��A����B����3�����������������Ă���A���e�̂����ɂ��Ȃ邵����ԒZ�k���ł��邳�B�܂�\���A�b�v�Ƃ����킯���v �@���������Ȃ���A���w������ɂ́A���ɂ���3�����������Ă������B �@�u�˂��A�ے��v �@�ЂƂA�ӂ��������ĉے��͗����オ�褃����o�[�����n���Ă������B �@�u���_���ł����Ƃ����A���낻��A�낤���B����̃T�[�N�����y���݂��ȁv �@�u�����l�v �@�ꓯ�A������Đ����グ���B
|
||||||||||||||||||||||||
| 4�@�S���Q������������ | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�c�c�Ƃ����킯�ŁA�c�O�Ȃ��炱��1�T�ԂɂƂꂽ�_���1�����Ȃ���ł����A�������V�K�̌_�Ƃꂻ���Ȍ����q���T���ł��܂����̂ŁA���������t�H���[���܂��B�ȏ�ŕ͏I���ł��v �@�u�_�Ƃ�Ȃ��Ƃ����̂́A���悤���Ȃ���ȁB�ł��A�����q��5���ł����Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ���邶��Ȃ��v �@�u���͎�������܂��B����1�T�Ԃ̐��тƂ��ẮA�V�K�_��1���ŁA���Ɂc�v �@���X�Ɖۈ����ϋɓI�ɕ��Ă����l�q�����Ȃ���A�c��1�ۂ�A�ے��́A���݂����ڂ�Ă���̂�}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤���B����Ƃ����̂��A����܂ʼnc��1�ۂ̖��T1��̒���́A�����̂悤�ɑS�����ϋɓI�ɔ������Ă����킯�ł͂Ȃ��A�ނ���`���Ƃ��Č��X�Ȃ�����Q�����Ă����̂���������B���ꂪ�ς�邫�������ƂȂ����̂��A3�T�ԑO�̕�����B���̂Ƃ��̏�i�́A���ł��ے��̋L���ɑN���Ɏc���Ă����B �@�u���T�͑S�R�_���ł����B�_���1�����i�V�ł��B�ȏ�ŏI���܂��v �@�u����ŏI���Ȃ̂��B���܂ł̂����ӂ���_�Ƃ�Ȃ��Ȃ�A�V�����ڋq��T����������Ȃ����B��э��݂ʼnc�Ƃ���Ƃ��A�Ƃ肠�����d�b���Ă݂�Ƃ����B�V�K�̂��q����Ƃ����A�|�C���g�����g���Ƃ����B�����Ă݂��v �@�ۂň�ԎႢ�Ј��̕��I���ƁA��y�i�炵���Ј������ӂ���悤�ɂ������B �@�u3���ł��v �@�u���ꂪ���O�̃_���ȂƂ���Ȃ�B�Ȃ�ł����Ƃ��Ȃ��v �@�u����ɂ��A�I�����_��悩��Љ�ꂽ�����q�����O�ɋ����Ă��������Ȃ����v �@�ʂ̎Ј����������B �@�u�����ƃR���^�N�g�͂Ƃ����̂��v �@�u�����B�ꉞ�v �@�u����ŁA������ƂɂȂ����B���Ȃ�I�����ꏏ�ɍs����B�����v �@�u����A����͂܂��c�v �@�u �R���^�N�g�Ȃ�Ď���ĂȂ��낤�B������_���Ȃ�B�����������O�͂����v �@�u������߂Ă�v �@�c��1�ۂł����ЂƂ�̏������A�b���Ղ�悤�ɐ����������B �@�u��������ȉ�c������ŁA��������ł��B���ꂶ�Ⴀ�݂邵�グ��c��B�����������Ȃ������āA������e�͂������������A�ӌ������߂��Ă���������Ȃ��ŁA���ނ��Ă邾������Ȃ��B�ے��A����ȉ�c�͂������ł��B���Ƃ����Ă��������v �@�����܂ł����ƁA���̎Ј��͍��荞��ł��܂��A��͂����Œ��f���Ă��܂����B �@�ۈ��S�������ނ��Ă��܂������ŁA���Ԃ������āA�悤�₭�ے��������J�����B �@�u�I����������������B�ǂ������̉ۂ̓`�[�����[�N���ǂ��Ȃ��Ƃ͎v���Ă����B �@���ꂶ�Ⴀ�A�ۂň�̂ƂȂ��Ďd��������Ƃ��A�ۑS�̂Ŏ��т��グ��Ƃ��A�Ƃ��Ă��]�߂Ȃ��ȁB�݂�Ȃł�낤��A�Ƃ����ӎ����Ȃ��ȁv �@�u�ʂɃ`�[�����[�N���ǂ��Ȃ��������āA�c�Ƃ͂ł��܂���v �@�u�����A�����B��c�����ďd�v�Ȏd���̈�����B�`�[�����[�N��������Ⴀ�A��c�������ɂł��Ȃ�����Ȃ����B��c�Ƃ����̂́A�����̐l�Ԃł�������Ɏ��g�ގd��������ȁv �@�u�����̐l�Ԃ��ꏏ�ɂ����Ă������Ƃ́A����ς�S�����C���ǂ��A�ϋɓI�ɎQ�����Ȃ��ƁA�����d���͂ł��Ȃ����c�v �@�����قǂ̏����Ј������������ƁA�ق��̎Ј����������B �@�u�����A��������ȁv �@�u�ł���c�ɂ͑S���Q�����Ă��邺�v �@�u�Q���͂��Ă��邯�ǁA�S���������̈ӌ��Ȃ�A�l���Ȃ�����Ă���킯�ł��Ȃ���B�^�ʂ�̕����ďI���Ƃ��v �@�u�ł��Ȃ��A���邾���ł��A�����������Ԃ���������B����ȏ�A���̕�Ɏ��Ԃ��������Ă����̂��Ȃ��c�v �@�����ł܂��S���A���ނ��āA�l������ł��܂����B���炭���̗l�q�����Ă����ے����������A �@�u�悵�A�������悤�v �@���������ė����オ�����B �@�u�݂�ȂɊ��z���������Ă��炨���v �@�u���z���A�ł����v �@���Ԃ������ɂ����˂�Ј��ɂ��ȂÂ��Ȃ���A�������B �@�u�����A���z������B��̏I���ɁA�S���Ɋ��z���������Ă��炤�B��������A�S�����Q�����āA�S���������������ƂɂȂ邾�낤�B�܂肳�A��c�ł͂����S������������Ƃ����K�������A�݂�Ȃňꏏ�Ɏd�������Ă���Ƃ����C�����ɂ��Ȃ�邾�낤�B�݂�Ȃł�낤����Ă����C�����ɂ��B�����Ȃ�`�[�����[�N���ǂ��Ȃ邳�v �@�u�ł��A���z�����Ă����Ă��c�B��������������ł����v �@�u���ł�������B��c�ɎQ�����āA�����Ŏv�������Ƃ����ł���������B�܂��Ƃ肠�����A���炭�����Ă���Ă݂悤��B����Ō��ʂ��ǂ��Ȃ�A����͂���Łc�E�v �@�u�ے��v �@3�T�ԑO�̕�̂��Ƃ��v���o���Ă����ے��́A�Ăт������ĉ�ɋA�����B �@�u�S���A���I���܂������ǁv �@�u����A���܂�B������ƍl���������Ă���������B���ꂶ�Ⴀ�݂�ȁA�����̂悤�Ɋ��z���������Ă���B�����I������҂͂��ꂼ��̎d���ɖ߂��Ă����v
|
||||||||||||||||||||||||
| 5�@�ӌ��Փ˂����� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�L�����y�[���̃R���Z�v�g��"���_�ɋA�낤"�Ƃ����̂͂ǂ��ł��傤�B���̒��A�o�u���A�o�u���ŕ����ꂽ���ʂ��A���̕s�i�C�ł�����A�����̑��������߂Ă݂���Ă������A������ł߂āA�������肵����Ђ��Ƃ������Ƃ��A�s�[������킯�ł��v �@���A���̉�c���ł͉c��1�ۂ�2�ۂƂ̍����ŁA�t�̔̑��L�����y�[���̊���c���J����Ă����B1�ۂ̎Ј����ӌ����q�ׂ���A2�ۂ̎Ј������������߂��B �@�u���_�ɋA�낤�Ȃ�āA�������̂��Ƃ������Ă�����A���̐��̒��̕ω��ɂ��Ă����Ȃ���B����ς莞��̐�[�����Ȃ��ƁB�l�͍����s��CS�A�܂�ڋq�������R���Z�v�g�ɂ�����ǂ����Ǝv����ł����v �@���̈ӌ���1�ۂ̎Ј����������B �@�u�l�̌����Ă��邱�Ƃ͌������Ȃ���Ȃ���B������A�ڋq�������Ă��Ƃ́A���q����̊�Ԃ��Ƃ͉��ł������Ă��ƁH������Č����Ȃ�ɂȂ���Ă��Ƃł��傤�B�E�`�̉�Ђ̎�̐��Ƃ��A�i���|�C���g�͉��Ȃ̂��Ƃ��A�����������Ƃ͂���Ȃ����Ă킯�H����ɗ��s����������Ă����̂��˂��B���Ղ���v �@���������āA���x��2�ۂ̎Ј������C�F��Ō����Ԃ����B �@�u�N�������Ȃ�ɂȂ�Ȃ�Č����ĂȂ����낤�B����ɁA�N�̂����i���|�C���g���Ă����̂����_�ɋA�낤�Ƃ������ƂȂ́B���������̂��đi���|�C���g���Ă����̂����B�܂����A���Î�Ƃ��ŁA��̂̏��i����낤���Ă�����Ȃ����낤�ˁv �@�u�c�Ƃɂ͂ˁA���q����Ɏd�|���镔���Ƃ����̂��厖�Ȃ�B���q����̌����Ȃ�ɂȂ��Ă邾������_���Ȃv �@�u�����Ȃ�ɂȂ��Ȃ����Ă����Ă邾�낤�B�����"���_�ɋA�낤�Ȃ�āA����ł��q����ɉ����d�|������Ă����B���q������~�������Ă���̂��A����Ȃ��Ƃ͊W�Ȃ����Ă����ȁv �@�u��������Ȃ����낤�B�l�������Ă�̂́v �@�u�����܂ŁI������߂��܂��v �吺��2�l�𐧂����̂́A�L�����y�[���̐ӔC�҂ł���A�c�ƕ��̖]�������������B �@�u�N�����A���������������������Ă�B�����͈ӌ���������ł͂��邯�ǁA�P���J������Ƃ���ł͂Ȃ����v �@�u����A�l�͎����̈ӌ��������������Łv �@�u�N�����̂���Ă���̂́A�ӌ��̂��Ƃ肶��Ȃ��B�P�Ȃ�A����I�ȗg������肾��v �@�u����A�������c�v �@�u�������A����Ȃ��B�N�����A������Ƙ_�_��c�����ĂȂ�����Ȃ����B�_�_�͂������������H������͂����肳���悤����Ȃ����B�܂�A�N�v ����������1�ۂ̎Ј��Ɍ������Č������B �@�u���_�ɋA����Ă����̂́A�ǂ������Ӗ��Ȃv �@�u�����ł��˂��c�B�o�u���̂���́A�������낻���Ȃ��̂��Ă������A�ڐV�������̂����ƁA����҂̂ق��ł��A�K�������~�����̂��A�K�v�Ȃ��̂łȂ��Ă��A���\�����Ă��ꂽ�킯�ł��ˁB�������]���Ă�����B���͂���������������Ȃ����A�ڐV�����������ᔄ��Ȃ��ł���ˁv �@�u����ŁH�v �@�u����ς�A����҂̃j�[�Y�ɂ��������̂����A���邢�̓j�[�Y����肷��Ƃ����̂��{���̎p���Ǝv����ł���B���������{���̎p�ɖ߂�Ƃ������ƂŁv �@�u�܂�A����҂��]�ޏ��i�A���邢�͖]�ނ��ƂɂȂ邾�낤���i�����Ƃ������Ƃ��ˁv �@�u�����A�܂��v �@�u���ꂶ��AB�N�v ���x��2�ۂ̎Ј��ɂ����˂��B �@�u�ڋq�����Ƃ����̂́H�v �@�u����Ⴀ�A���q���E�`�̏��i���āA�ق�Ƃɖ������Ă��炦��悤�ȏ��i�����Ƃ������ƂŁc�v �@�u�܂�A����҂��ق�Ƃɗ~�����Ǝv�����i���A�Ƃ������Ƃ��낤�v �@�u�����c�v �@�u����Ȃ�N����2�l�Ƃ��A�����ӌ������Ă��ƂɂȂ邶��Ȃ����v �@�u�����ł��ˁv �@�u�����A���t�łǂ��\�����邩�Ƃ����_���Ⴄ�������낤�v �@�u�����Ȃ�܂��ˁv 2�l�A��������킹�Ă��Ȃ������B �@�u�ǂ����s�тȓ��_�������Ƃ������Ƃ��ȁB���������A�N�����B�ӌ��̏Փ˂Ƃ����̂͑傢�Ɍ��\�Ȃ��Ƃ���B����ɂ���ĉ�c���i�s����B�ł��ȁA�ӌ��̏Փ˂ɂ�2�����B�ЂƂ́A�ق�Ƃ��̈Ӗ��ł̈ӌ��̏Փ˂ŁA�����ЂƂ̓E�\�̈ӌ��Փ˂��ȁB�����Ă݂�A����I�ȁA�g������肾�B���q����̌����Ȃ�ɂȂ�Ƃ��A�������̍l�����Ƃ��A����͗g������肾�ȁB���݂��A�_�_�̂͂��ꂽ�Ƃ���Ō��������ĂĂ����悤���Ȃ����낤�B�܂Ƃ܂���̂��A�܂Ƃ܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�t�ɁA�_�_�͉������Ă������Ƃ���������c�����ċc�_����A���\�܂Ƃ܂���̂ȂB�������낤�v �@�u�m���ɁA���̒ʂ�ł��v 2�l�̎Ј����[����ł��Ȃ������B �@�u���ꂶ�Ⴀ�ӌ�����v�������Ƃ����A���낻��R���Z�v�g���܂Ƃ߂悤����Ȃ����v
|
||||||||||||||||||||||||
| 6�@�s���v������� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�E�`�̉ۂ̈ӌ����܂Ƃ߂�ƁA���iA�̓W���ɂ����Ƃ��L���X�y�[�X�������Ăق����Ƃ������Ƃł��B�Ȃɂ���A�E�`�̉�Ђ̎�͏��i�ł����A����̏t�̃L�����y�[���̓W����ł��A�ϋɓI�ɃA�s�[�����邱�ƂŁA����ɔ��㑝�ɂȂ���ł��傤�v �@�u�����珤�i�`���N�̉ۂ̈�����������āA����͂�����ƘI������Ȃ����B�ނ��돫���̂��Ƃ��l����A�E�`�̏��iB�̖M��A2�`3�N������z�������i�Ȃ���A��苭���A�s�[������ׂ�����Ȃ����v �@�u�������˂��A���㑝��_���ď��i�W������J������A����ς��Ԃ̔���؏��i�ɗ͂�����ׂ�����v �@�u���₢��A���㑝�Ƃ����̂Ȃ�A�����ЂƂL�тĂ��Ȃ����i���A�s�[����������A�S�̂Ƃ��Ă̐L�тɂȂ����Ȃ����v �@�u����������Ȃ�A���iA�Ƃ��A���iB�Ƃ��Ɍ��炸�A�ǂ̏��i�����ՂȂ��W������ׂ����낤�v �@�u�P�ɍ�����Ă邩�ǂ����������Ƃ��A��̂��Ƃ��l�����ق���������Ȃ��v �@�u����ăi���{������˂��v �@�u�܂��A�܂��B������Ƒ҂��Ă����v �@���������āA��c�̎Q���҂𐧂����̂́A�c������w�߂Ă���c��1�ۂ̉ے��������B �@�u�݂�Ȏ����̉ۂ̗��v���\���Ĕ������Ă��邾�����Ⴀ�A���̉�c�܂Ƃ܂�Ȃ���B�Ȃ��W��������̂����Ă����ړI���A�ǂ����݂�Ȃ̂Ȃ��ł͂����肵�Ă��Ȃ��悤���ȁB������A���ꂼ��̉ۂ̗��v�����������ɂȂ���Ȃ����v �@�u�������ے��v �@1�l�̎Ј����������B �@�u�W��������̂͐���̃L�����y�[������c�Ō��܂������ƂŁA�Ȃ���邩���Ă����A�̑��̂��߂ł��傤�B�܂蔄�㑝�̂��߂��Ă킯�ł���ˁv �@�u�m���ɂ������B�������ˁA���ꂾ�����Ⴀ�_���ȂB����̉�c�́A���㑝�̂��߂ɂ͉�����邩�Ƃ����̂��e�[�}�������B�����̉�c�́A�W������ǂ����{�����炢���̂��A���̂��ߏ����Ƃ��ĉ���������炢���̂��A���̃g�E�E�h�E�E���X�g������āA�e���ɖ������S���邱�Ƃ��B�����Ă݂�A���ۂɍs�����N�������߂̉�c���B�������낤�H�v �@�u�����ł��ˁv �@�u���ۂɍs�����J�n����ɂ́A�W��������ړI�͉������Ă������Ƃ��A���[���A���@�艺���ĔF�����Ȃ��ƃ_�������Ă��Ƃ��v �@�u�͂��c�v �@�u�����ł��B�Ȃ���邩���l����O�ɁA�܂������c�����邱�Ƃ���n�߂悤���v �@�u����c���ł����H����������́A�����e�ۂŏ\���Ɂv �@�u�܂��A��������v�@ �@�Ј����������悤�Ƃ���̂��Ղ��āA�ے����������B �@�u���ꂩ��e���i�̒����ƒZ���A����Ɋe�ۂ̒����ƒZ�����A���ꂼ��S���ɏq�ׂĂ��炨���v�A�u����łǂ��Ȃ���Ă�����ł����H�v �@�u�����̃C���[�W�A���ʂ̃r�W���������v �@�Ј������͈�l�ɁA�����Ȃ��킩���A�Ƃ�����������A�ے��͂��܂킸1�l�̎Ј������Ȃ������B �@�u���ႠA�N����v�@ �@�u�����ƁA���Ⴀ���̕��ł́A�܂����iA�̒����Ƃ��Ắ\�\�v�@ �@�Ƃ��������A�ے��̎w���ǂ���ɉ�c�͐i�s�����B�����āA�S���̔������I������Ƃ���ŁA�Ăщے����w���������B �@�u���ꂶ�Ⴀ���x�́A�݂�Ȃ��l���鏫�����Ƃ����̂\���Ă���B�W����I������i�K�ŁA�����̉ۂ������Ȃ��Ă��Ăق����Ƃ��A�����ς���Ăق����Ƃ����A�����r�W�������B�������Ƃ��ẮA���������L���̂��A�Z�������P����̂��A����2���l������ȁv �@�u����\���Ăǂ������ł����H�v �@�u�����炳�A��X�̋��ʂ̏����r�W���������B�܂�ˁA���ʂ̃r�W�������ł���A���̃r�W�������������邽�߂ɂ́A�W������ǂ����{�����炢���̂��A�c�_���ł��邾�낤�v �@���������āA�Ј������͂��炭�l������ł������A�₪��1�l�̎Ј��������������B �@�u�Ȃ�قǁI�����Ȃ�W������ǂ����邩���l�����Ȃ��āA���̐�̂��ƁA�W�������邱�ƂŌ�����ǂ��ς��邩���A�܂��l����킯�ł��ˁB���ꂪ�܂�W��������ړI�ŁA���ꂪ���܂�A�W������ǂ��������̂ɂ��邩�����܂��Ă���킯���v �@�u�������A�S�������ʂ̖ړI�����Ă�v �@�u������e�ۂ̗��Q�̑Η��Ȃ�Ă��Ƃ��Ȃ��Ȃ�v �@�Ј������X�Ɛ���������̂����āA�ے����������B �@�u���Q�̑Η����Ȃ��Ȃ�A�������ӌ����܂Ƃ܂�̂������Ȃ�B�ӌ����܂Ƃ܂�A���Ƃ͏����̂��߂ɉ�������̂������߂邾���B�������낤�B���Ⴀ�A�܂�A�N����n�߂Ă���v �@�ĊJ���ꂽ��c�́A���̌�͑�Ȃ��i�݁A����ɋ��ʂ̃r�W�������쐬���ꂽ�̂��́A��c�̃e�[�}�ł������A�������ڂ̌��肪�Ƃ�Ƃq�ł͂��ǂ����̂������B �@�u�W����Ɍ����Ă̍s���v����ł������Ƃ����A�Ō�ɑS���ɖ������S���āA���ꂼ��̏������ڂ̒S���҂����߂āA���悢�悱�̉�c���I�����B�ĊO�����I��肻������Ȃ����B�ŏ��͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ǝv�������ǂȁv
|
||||||||||||||||||||||||
| 7�@�`�[�����Ƒł����킹���� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u���q����Ƃ̏��k��4��ŁA���ς̍쐬��3���ł����B�ȏ�ŁA��T�̉c�Ƃ̕͏I���ł��v �@�u����őS���̕͏I������ȁB���ꂶ��A���������ӌ��A���邢�͉����C�Â������Ƃ��������炢���Ă���v�c�Ɖۂ̌W�����A�����̎Ј��Ɍ������Ă����˂����A5�l�̕����̂����A�N�ЂƂ蔭�������߂�Ј��͂��Ȃ��B �@�u�ȂA�������N�����Ȃ��̂��B���T1��A���̃`�[���̒�����J���Ă��邯�ǁA�����������́A�݂�Ȃ��玿��Ƃ��ӌ��Ƃ��A�ł����߂����Ȃ��ȁv �@�u����Ƃ����Ă��c�v �@�����̒���1�ԔN��̎Ј��������������������A�r���ł�߂Ă��܂����B �@�u�������AA�N�B���܂�Ȃ�����A�����Ă݂��v �@�u����A���́`�B�����Ȃ������Č����Ă��A������菤�k�͈̉���ȂƂ��A�܂����̒��x�̂��Ƃ����c�v �@�u���̐l�͂ǂ��H�S���̕��āA�����v�������Ƃ͂Ȃ�� �@������5�l�́A�݂ȉ����ق��Ă��邾�����B �@�uB�N�v�@ �@�u�͂��v�@ �@�Ăꂽ�Ј��́A�������悤�ɌW���̂ق����������B �@�u�N�́A�Ⴆ�Ηׂɍ����Ă���C�N�ɁA��������Ƃ��͂Ȃ��́H�v �@�u�����`�A�ʂɁv �@�u���Ⴀ�AC�N��D�N�ɉ����Ȃ��H�v �@�u�����A���ɉ����v �@�u���`��A�������Ȃ��v �@���������āA�W���͘r�g�����Ȃ���A�����l���Ă�l�q���������A�ˑR�v�������悤�ɁA1�ԔN��̎Ј��ɂ����˂��B �@�u����������A�N�B�����AB�N���Ă̂��q����d�b�ɌN���łĂ����ˁv �@�u�͂��v �@�uB�N�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��A�Ȃ�Č����Ă����ǁA���̓d�b�͉��������́H�v �@�uE�Ђ���̓d�b�ŁA�E�`�Ƃ̐V�K�_��̌��ł��B��T�����炩�猩�ς������Ă��邻���ł����A������ƕ����������Ƃ�����Ƃ������ƂŁc�v �@�u����ŁAB�N����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ɠ������ˁv �@�u�����BB�N���ǂ�Ȃ��q����ƁA�ǂ�Șb�����Ă���̂��A���͂����Ƃ��m��܂���B���i�ɂ��Ă̈�ʓI�Ȃ��ƂȂ玄�������܂����ǁA�ʂ̈Č��ƂȂ�Ɓc�v �@�u�ׂ͉�������l���A�S�R�킩���Ƃ����킯���ˁB���̂ЂƂ͂ǂ��H�ׂ̐l�����A��������Ă���̂��A�����Ƃ킩���Ă���HB�N�́AC�N������������Ă��邩�m���Ă�v �@�u�܂��A�����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���낤�Ƃ͎v���܂����ǁA�ǂ�Ȃ��q����ɃA�v���[�`���ĂāA�ǂ�Șb�����āA�ǂ��܂Řb���i��ł�Ƃ��A�����܂ł͒m��܂��v �@�u�܂����A�E�`�̃`�[�������A��������Ă邩�悭�킩���A�Ȃ�Ă��Ƃ������l�͂��Ȃ����낤�H�v�@ �@5�l�Ƃ��A�Ԏ��������ɖق��Ă���̂����āA����ׂȂ���A�W���͂��ߑ����ЂƂA�����B �@�u���ꂳ�����悭�킩���A�Ƃ����킯���B���ꂶ�Ⴀ�A������ӌ����łȂ���ȁv �@�u�W���v �@��y�i�̎Ј�����������Ĕ��������߂��B �@�u�E�`�̃`�[���Ƃ����̂́A�ǂ����`�[���ŋ��ʂ̖ڕW�Ƃ������A���莖���Ƃ������A�����������̂��Ȃ��悤�Ɏv����ł����B������A�`�[���ȂƂ����ӎ����ŁA���݂���������Ă邩���킩��Ȃ��Ǝv����ł���B���ꂪ�킩��Ȃ�����A���̕�Ŏ�����ӌ����A�����łȂ��v �@�u����B���ꂾ��AA�N�B�Ȃ��Ȃ��������Ƃ������˂��B�����o�[�����݂��ɉ�������Ă���̂��킩��Ȃ��B������A�`�[�������A����ڕW�ɁA�ǂ������Ă���̂����킩��Ȃ��B�����������Ƃ��ȁv�����ŌW���͈�ċz�����āA�����̊�����n���Ă��瑱�����B �@�u�Ƃ������Ƃ́A�N�����A��������Ă�̂��A�����o�[���m�ł킩�肠����悤�ɂ�������킯���B�������낤�v �@�u�ł��A�ǂ�����āv �@�u�������A���̒���𗘗p�����v �@�u������������Ă��A�킩�肠����悤�ɂ͂Ȃ�܂����v �@�u�H�v��������̂��B���ꂩ�����ł́A�O�̏T�̉c�ƌ��ʂȂ�āA���Ȃ��Ă����B���̂����A����1�T�ԂŎ����͉�����낤�Ǝv���Ă���̂��A�������Ă���B�e�����o�[��1�T�Ԃ̍s���v��\�����ɂ���킯���v �@�u�Ȃ�قǂˁB�����Ȃ�A�ׂ͉�������l���A�����Ă���킯�ł��ˁB���q����̖₢���킹�Ȃ��A�S���҂ł͂Ȃ��Ă����ł���悤�ɂȂ邵�v �@�u�������A���ꂾ������Ȃ��v �@�W���͂Ȃ����������B �@�u�`�[���Ƃ��ẮA���ʂ̍s���v����A���̒���ō���Ă��܂����B�`�[���̏T�s���v��\�݂����Ȃ��̂��A���̏�ō���āA�݂�Ȃŋ��ʂ̂��̂Ƃ��Ď����A��B������������ɂ��Ă݂悤��v �@�u�����ł��ˁB���Ђ��܂��傤�v �@5�l�̕�������l�ɂ��Ȃ����̂����āA���x�͌W�����Ί���ׂĂ����B
|
||||||||||||||||||||||||
| 8�@�ƍە���̈ӎv��������� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�c�Ɖۂ̃t���A�̈�p�ɂ���~�[�e�B���O���[���ŁA�c�Ɖۂ̂`�ے��ƊJ���ۂ̂a�ے��Ƃ��A�e�[�u��������ł��݂��̊�����������܂܁A�ق荞��ł��܂��BA�ے������������������Ƃ����A���傤�ǂ��̂Ƃ��A�]���c�ƕ������h�A���J���ē����Ă��܂����B �@�u�N������l�A���������������Ă���B�c�ƂƊJ���ƂŁA�ے����m���P���J�����Ă�����āA�O�ŎЈ��������S�z���Ă邼�BA�ے��A�ǂ������v �@�u����̔̑���c�ŁA����グ�������Ă��錻����Ȃ�Ƃ��ŊJ���悤�Ƃ������ƂŁA�b���������ł��傤�B����ŁA�V���i�̊J���ɍۂ��ẮA�c�ƂƊJ���Ƃŏ����������A����鏤�i�������Ȃ������Ă��ƂɂȂ�܂�����ˁB����ō��A�ǂ�����ď�������i�߂Ă������AB�ے��Ƙb�������Ă��ł����v �@�u����łǂ����ăP���J�ɂȂ���v �@���x�͊J����B�ے��������܂��B �@�u�E�`�̂ق��Ƃ��ẮA�����̏��i�ɑ��Ă��q���ǂ�Ȋ��z�������Ă��邩�Ƃ��A���q����̃j�[�Y�͉����Ƃ��A���������ڋq��Ȃ����A���̓_�A�������q����Ɛڂ��Ă���c�Ƃ͏��������Ă邾�낤����A������o���Ă���ƌ����Ă��ł����v �@������āA��������A�ے��������Ԃ��܂��B�@ �@�u����͊J������Ƃ��āA�ӔC�����ɂȂ��Ȃ����B�I�������͔���̂��{�ƂŁA���̂͂������Ȃ���B�C�x���g������āA�̑�������Ă�̂ɔ���s�����L�тȂ��̂́A���i�ɖ�肪������Ă��Ƃł��傤�B���q����ɋC�ɓ����Ă��炦�鏤�i�����Ƃ������Ƃ��A�܂��l���Ă�v �@�u������A���q����ɋC�ɓ����Ă��炦�鏤�i����邽�߂ɂ́A���q����Ɛڂ��Ă���c�Ƃ���A�ǂ��������i���]�܂�Ă���̂��A����������E�`�ɂ͂Ȃ����Č����Ă�ł��傤�B���i�͂����邩�ǂ����A�������Ȃ̂��A������c�Ƃ��炾���Ă����v �@�u�ǂ��������i�������̂����l����̂��A�I�^�N�����̎d���ł��傤���v�@ �@�u�킩�����A�킩�����v �@�悤�₭�]��������2�l�̌����������~�߂ɓ���܂����B �@�u�����̌������͂悭�킩�����B�Ƃ���ŁA���q����̃n�[�g�Ƀq�b�g���鏤�i�𐢂ɏo���������A���̂��߂ɂ͏����W�Ȃ�A���͂��K�v���Ƃ����_�ł́A�ӌ��͈�v���Ă�낤�v �@�u�������v �@�u���R�A�����Ȃ�ł��傤�v�@ �@�u����Ȃ�A���̖��������ł����B�m���ɏ��̕��͂Ƃ����̂́A�c�Ƃ����̂��A�J�������̂��A���ꂼ��̐ӔC�A�������N���X�I�[�o�[���镔��������A���݂��ɐӔC�̂Ȃ���t�������ɂȂ��ȁB�����炱���A��������đ��k���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��킯���B�������낤�A�`�ے��v �@�u�܂��A�����������ƂɂȂ�܂����v �@�u�{���������A�o���Ƃ�����ȏ�͕��S�𑝂₵�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B�ł��ȁA�J���ۂɂ͂ł��Ȃ����Ƃ�"����"�Č����̂����������A���Ƃ����ĉc�Ƃɂ������S�������t����̂����ӔC�Șb����B�������ł���Ă���Ƃ������z�łȂ��A�������łł��邱�Ƃ͉����Ƃ������z�ł���������Ȃ����B�ӔC���ǂ��炩�ɉ����t�����Ȃ��āA�o���ŐӔC���Ƃ�悤�ɂ�����ǂ������v �@�u�Ƃ����ƁH�v �@�u���݂��ɂ܂��A���������̂ł��邱�Ƃ͂ȂA���ӕ���͉����A������l���Ă���B����ɉ����Ė������S�����āA�o�����ӔC�������āA���ꂼ��̖������ʂ����B����ł�������Ȃ����B���ꂶ��A���Ƃ͔C������v �@�u������Ƒ҂��Ă���������v�@ �@�~�[�e�B���O���[������o�Ă������Ƃ���]���������AA�ے�������ĂĎ~�߂悤�Ƃ��܂��B �@�u�J���Ɖc�ƂƂ̊ԂŌ��ʓI�ȃR�~���j�P�[�V�������ł���悤�ȁA���������d�g�݂��l���Ă����B���̌��Ɋւ��ẮA�c�Ƒ��̂��ׂĂ̌����͌N�ɂ���Ǝv���āA�D���ɂ���Ă���B���ꂶ�Ⴀ�v �@���������āA�]�������͏o�Ă����܂����B �@���ƂɎc���ꂽ2�l�̉ے��́A�܂��e�[�u��������ō��蒼���[�[�@ �@���ꂩ��30���قǂ̂��AA�ے��̓~�[�e�B���O���[������łĂ���Ȃ葁���A�]�������̃f�X�N�ւƋ߂Â��Ă��܂��B �@�u�����A�I���܂�����v �@�u���̊炩��@����Ƃ���A���܂��܂Ƃ܂����悤���ˁB�ŁA�ǂ��Ȃ����H�v �@�u�����̂��������Ƃ���A���݂��ɂł��邱�ƂS���悤�Ƃ������ƂŌ��܂�܂����B�c�Ƃ̂ق��ł́A�E�`�������Ă���ڋq�f�[�^�����I�ɕ��͂��A���̎������J���ɓn�����Ƃɂ��܂����v �@�u�J���̂ق��́H�v �@�u�E�`�̎��������Ƃɏ��i�R���Z�v�g����邱�ƁB�܂��A���i���ւƐi�ޑO�ɁA�K���E�`�ɑ��ăR���Z�v�g�̃v���[�������āA���ӂ邱�ƁB�ȏ�ł��v �@�u����J����v
|
||||||||||||||||||||||||
| 9�@�i���m�F������ | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�ڋq�Ǘ��ƈ���Ō����Ă��A�P�Ɍڋq�̎�����Z�����Ǘ����邾���ł́A�������Ė��ɂ͂������B���������R���s���[�^���g���āA�V�����ڋq�Ǘ��V�X�e����������A�Ⴆ�E�`�̉c�ƃ}�����ǂ̂��q����ɁA�ǂ�Ȃӂ��ɃA�v���[�`���Ă����̂��A�����������f�[�^���Ǘ�����K�v������ȁv �@�c�Ɖے��̘b�́A���ꂱ��15���������Ă��܂����A���̊ԁA�������̉ۈ��B�͂Ƃ����A���X���Ȃ�������A�u�����ł��ˁv�Ƃ����Â����������ŁA�ӌ����q�ׂ�҂͂ЂƂ�����܂���B �@�u�R���s���[�^�ňꌳ�Ǘ����邱�ƂŁA�Ⴆ�ǂ̒n��ɃE�`�̂��q�������̂��A���邢�͂ǂꂭ�炢�̗\�Z�̂��q�������̂��A�����������f�[�^���ȒP�ɂłĂ��邵�A�̑��ɂ����p�ł���Ƃ����킯���v �@�u�ے��v �@����܂ł����ƕ������ɉ���Ă����ۈ������ł����A�ے��̘b����i�������Ƃ���ŁA���߂ĂЂƂ肪�������܂����B �@�u����ŁA�Ǘ����ڂ͂ǂ����܂����H�v �@�u����́A���ꂩ��N�����̈ӌ����Ă��猈�߂��B���̃v���W�F�N�g���X�^�[�g���Ă���1����������A���낢��ƒ��ׂ����Ƃ����邾�낤�H�v �@�u�����A�ʂɁc�c�v �@�u�ʂɂ��āA�ǂ��������ƁB�ӌ��Ƃ��A�����Ȃ��́v �@�u����`�A���ɉ����c�c�v �@�u�����Ȃ����āH���ꂶ�Ⴀ�N�́A����1�����A�����Ă��́H�v �@�u����́A���̃v���W�F�N�g��c�ɎQ�����āA�ے��̘b���āA�Ȃ�قǂƁc�c�v �@�u���ꂾ���H�v �@�u�����v �@�u���̎҂͂ǂ��H ����1�����ŁA�Ⴆ�Α��Ђ̌ڋq�Ǘ��V�X�e�����ǂ��Ȃ��Ă�̂����ׂ�Ƃ��A��发���ĕ�����Ƃ��A�E�`�̎Ђ̌���ׂ�Ƃ��A��������Ă�낤�H�v �@�ے������������˂Ă��A������҂͒N�����܂���B �@�u�����A�����B���ꂶ�Ⴀ�N�����́A���̃v���W�F�N�g�Ɋւ��ẮA���̎d��������ĂȂ����Ă��Ƃ���Ȃ����v �@�u�ے��B�����͌����܂����ǁc�c�v �@�ЂƂ�̎Ј����������������܂������A�r���ł�߂Ă��܂��܂����B �@�u�������H�������猾���Ă݂��v �@�u���̉�c��������4��ڂł����ǁA�����ے��̉����������̉�c�ł�������v �@�u�����A�����B�܂�ʼnے��̓Ɖ���ł���B�����Ƃ��A�ے��̃E���`�N�̐[���ɂ͉�X�͂��Ȃ�Ȃ��킯�ł����A�ے��̘b���̂͗L�v�Ȃ�ł����ǁc�c�B�������̂��ƁA�ے������ׂēƒf�Ō��肵�Ă���܂��B�Ȃ܂���X�̈ӌ������͂��������c�c�v �@�u�����ł���A�ے��B���̂Ƃ���A�������ׂ���Ă����Ă��A���ꂾ���傫�ȃe�[�}�ɂȂ�ƁA�����������Ă����̂��킩��Ȃ��āB����̉c�Ƃ��Z�����āA����ł����A�v���W�F�N�g�̎d���͉�c�ɎQ�����邾�����Ă������ƂɁv �@�u���̐�A�v���W�F�N�g���ǂ��Ȃ邩�A���I���̂��������Ȃ��ł�����ˁB�ǂ������܂ʼnے��̃����}����c��������ł�����A�����͉ے����p�b�ƌ��߂��Ⴆ�A����ł��̃v���W�F�N�g���i���ƂɂȂ邵�A��X�ɂ͖{�Ƃ����邱�Ƃ����v �@�u����Ⴀ�A�������Ȃ��v �@�����ے����Ԃ₢���A���傤�ǂ��̂Ƃ��A��c���ɖ]�������������Ă��܂����B �@�u�����A�ǂ����Ă����Ɂv �@�u���̃v���W�F�N�g�̕����������ɓ����Ă��Ȃ�����S�z�ɂȂ��ĂˁB�Ƃ���ŁA�������Ȃ��āA�ǂ��������ƁH�v �@�u���́A�����ɂ��郁���o�[���[�[�v �@�ЂƂƂ���ے����玖����ƁA�����͂ЂƂA�ӂ����Ȃ����āA���������܂����B �@�u�ے��̘b���ďI���A�Ƃ�����c�͖�肪����ȁv �@�u����ς�ے��̃����}���Ƃ����̂��v �@�������������������o�[���������܂����B �@�u�����}����c�Ƃ����̂́A�K�����������Ȃ��B���������H�v����ˁB�����o�[���������ʂ������A�ӌ��\����̐����������B���̂����ŁA�ӌ��̎��܂Ƃ߂�A�v���W�F�N�g�̕����Â��͉ے����������B����̓����}���ł��A�ƒf�ł�������B�ے��ɂ́A���ꂾ���̒m�����E���`�N���������B�������A�����o�[�������ɕ���Ȃ�A�ӌ��\����ɂ́A�d�������Ȃ�����ȁB�N���������Ȃ���A���̃v���W�F�N�g�͂����Ƃ��i�܂Ȃ���v �@���������āA�����o�[�ꓯ�A���ނ��Ă��܂��܂����B �@�u���������傫�ȃv���W�F�N�g��i�߂�Ƃ��ɂ́A�����A�������ł���������A���C�悭�R�c�R�c�ƍ�Ƃ�i�߂Ă������Ă������Ƃ��A�Ȃɂ��厖�Ȃ��ƂȂB����̉�c�����ŏI������悤�Ȏd������Ȃ�����B���������d���̐i�ߕ����ł���悤�ɍH�v������ǂ������B�ے��A���Ƃ͔C������v �@���������āA�]�������͍������Ƃɂ��܂����B�c���ꂽ�����o�[�݂͂ȁA�ے������߂Ă��܂��B �@�u���́A�ЂƂl���Ă邱�Ƃ�������v �@�ے��͂��������ƁA��ċz�����āA�����o�[�̊�����n���܂����B �@�u����A���̉�c�̎�v�c��́w���ǂ��Ȃ��Ă�́H�x�Ƃ������Ƃɂ��悤�B�����Ă݂�A�i���̊m�F���ȁB���̂��߂ɁA�݂�Ȃɂ͖���A�s����������Ă��炤���Ƃɂ��悤�v �@�u�s�������H�v �@�u�܂�A���̃v���W�F�N�g�̂��߂ɁA���̓��͉����Ԕ�₵�����A�ǂ��֒����ɍs�������A�ǂ�ȍ�Ƃɂ��Ă��̂��A���̖����̋L�^���A1�T�Ԃ��ƂɁA���̉�c�ŕ��Ă��炤�B��������A����1�T�Ԃ́A�݂�Ȃ̎d���̐i����c���ł��邾�낤�v �@�u�t�Ɍ����A�s�����������ȏ�́A��X�������A��������̎d�������āA���̃v���W�F�N�g��i�߂Ȃ�������Ȃ��Ȃ�A�Ƃ����킯�ł��ˁv �@�u����������������p������������Ȃ��v �@�u���������킯���v �@�ے��́A�u�V���V���v�Ƃł������������ȕ\����ׂĂ��܂����B
|
||||||||||||||||||||||||
| 10�@�u�����A��ρv�ɑΏ����� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�ے��A��ςł��v �@�c�Ɖۂ̎Ј��̂ЂƂ肪�Q�Ă��l�q�ŁA�ے��̃f�X�N�ɋߊ���ė��܂��B �@�u������A�Ђ��s�n����o�������������Ă�����v �@�u�������āB�܂�|�Y���Ă������Ƃ��H�v �@�u���̂悤�ł��v �@2�l�̂������t�����ۈ��������A���������ɏW�܂��āA�ے��̃f�X�N�����͂�ł��܂��܂����B �@�u�|�Y���āA�ǂ��������Ƃ��v �@�u����͂��̂��Ƃ��v �@�u�ے��A�ǂ����܂��傤�v �@�u�����A�����N�����B�Ȃ��Ă����ɏW�܂��Ă���v �@�u�����ĉے��B�����ɂ���̂́AA�ЂƎd����ŊW�̂���҂ł���v �@�u�|�Y�Ƃ����͖̂{���Ȃ̂��H���ڂ̒S���҂͒N���H�v �@�u���ł��v �@�ЂƂ�̎Ј�������������ƁA�ꓯ�̖ڂ����������ɁA���̎Ј��̕��ւƌ����܂����B �@�uA�N���S�����B���̏��͖{���Ȃ̂��H�v �@�u�{�������Č����Ă��A�������̏����Ă����킯�ł͂Ȃ����B�m���ɁA����͗����Ă���Ă����b�́AA�Ђ̕����畷���Ă��܂����v �@�u����Ȃ��Ԏ����ȁB�����ɓd�b���Ċm�F���Ă݂��v �@�ے��Ɍ����āA�Q�Ă�A�N�͎����̃f�X�N�ɋ삯�߂��čs���܂����B �@�u�Ƃ���ŁA���̏o���͂ǂ����v �@�u������B�Ђ̎d����ے��ł��B�������d�b�Řb�����Ă����Ƃ��ɁA���������Ă��ꂽ��ł��B�ǂ����s�n����o�������������āv �@�u�����Əڂ����b���Ă݂��v �@�ے��̃f�X�N�����g�ސl�_���炻�����������オ��ƁA�����ЂƂ�Ј����f�X�N�ւƋ삯�߂��čs���܂��B �@�uB�Ђ̘b���Ă��A�������Ė��ɂ͂����낤�B������AA�Ђ���̕ۏ؋��͉������Ă�̂��Ȃ��v �@�u�N�A�o���֍s���āA�ۏ؋��̂��ƂƂ��A����|�����������炠��̂��A�����ɒ��ׂĂ�����Ă���v �@�ے��ɖ������āA�܂��ЂƂ�Ј����삯�o���܂������A����Ⴂ�ɐ���̎Ј����߂��ė��܂����B �@�u�ے��A�_���ł��BB�Ђ̎d����ے����A�ڂ������Ƃ͒m��Ȃ������ł��v �@�u�ے��A����Ȃ��Ƃ͂�������A���ۑS�̎藧�Ă��u��������������Ȃ��ł����B�@���։����𗊂݂܂����v �@�u�ے��v �@�����ցA�S���҂�A�N���߂��ė��܂����B �@�u�_���ł��B���d�b������ł����A�N���o�Ȃ���ł���B�ǂ����܂��傤�v �@�u�ǂ����܂��傤����Ȃ���B���O���S���҂Ȃ���A�v�������邱�Ƃ����邾�낤�v �@�u�I����ӂ߂Ȃ��ł���������B�I����A�Ђ�ׂ����킯����Ȃ���ł�����v �@�u����Ȃ��Ƃ��P�����u����ق����悾��B�ǂ����܂��傤�A�ے��B�Ή���́H�v �@�u�����Ƒ�����������Ȃ����B���������ǂ������v �@���܂��ܒʂ肩�������J���ۂ̉ے����A�����̗ւ̒����̂������ނ悤�ɂ��āA�q�˂܂����B �@�u�Ȃ��E���������Ă���l�q����Ȃ����B���������H�v �@�u�����A����v �@���O�҂ɐq�˂��āA�悤�₭�ے��́A���܂ʼn��Y��Ď�藐���Ă��������ɋC�Â����悤�ł��B �@�u�ے��v �@�܂��ЂƂ�A�Ј����߂��ė��܂����B �@�u�o���֍s���ė�����ł����A�����Ɋm�F�Ȃł��Ȃ����āA�{���܂�����v �@�u�������A�킩�����B�Ƃ���ŁA������ƍ��Z�����̂Łv �@���������āA�J���ے��������̂���ƁA�܂��̎Ј��ɌĂт����܂����B �@�uA�ЂƂ������̂���҂����c���Ă���v �@2�`3�l���l�_���甲����̂�҂��Ă���A�ے����ڂ��J���܂����B �@�u�����W���͂����肵�Ȃ����̏ŁA�Ή�����u����͖̂����Șb���B�܂��A���ꂩ��1���ԂŁA�����͂ǂ����A�Ƃ����̂��͂����肳���悤�BA�N�A�N�͂��ꂩ��A�Ђɏo�����āA�S���҂��猻�݂̏��ڂ��������ė��Ă���B���ꂩ��N�́A�o���ɗ���ŁA�ۏ؋��Ɣ���|�����̊m�F���B�c��̎҂��A���Ђ��ǂ������Ή������Ă��邩�A�����W�ɓ����Ă���B������1���Ԍ�ɉ�c���ɏW���B���ꂩ��Ή���̌������B��c�̂��Ƃ́A���ꂼ��̖����ɉ����āA�Ή��ɓ����Ă��炤�B�݂�Ȃ��̃X�P�W���[���ŗ��ނ�v �@�������Ĉ�U�͉��U���āA�������S�𖽂���ꂽ�Ј��ȊO�́A�e�����ꂼ��̃f�X�N�ւƈ����g���܂����B������1���Ԍ�A��c���ł́\ �@�u����Ŏ����W�͂͂����肵���ȁB���ʂ́AA�N�������ƂȂ��āAA�Ђ̓����ɐ₦���ڂ�z�邱�ƁB�����ω�����������A�����Ɏ��ɘA�����Ă���B���̂ǁA�S���W�����ĉ�c�����K�v�͂Ȃ����낤�B���ꂩ��A�N�ƌN�Ƃ́A�o���A�@���ƘA�g���āA���ۑS�̕�����������āA���ł����{�ł���悤�ɂ��Ă����Ă���A���̂Ƃ�����ׂ����Ƃ͈ȏゾ�ȁv �@�u�ے��A��X�́H�v �@�������S����͂��ꂽ�Ј����q�˂�ƁA�ے��͗��������ē����܂����B �@�u���̏ł́A���l���ő����قǂł͂Ȃ��B�܂��AA�Њ֘A�̏��ɋC��z���Ă�����x�ł������낤�v
|
||||||||||||||||||||||||
| 11�@����c�������Ȃ� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�݂Ȃ���ɂЂƂ�Ă�����܂��B���̕���������������Ă݂悤�A�Ƃ����C�͂���܂��B �@������1���j���ɊJ����Ă��镔����̐ȏ�A�]���������ˑR�A����Ȕ����������̂����̔��[�ł����B �@�u������������āA�ǂ��������ƁH�v �@�c�����̐ꖱ���q�˂�ƁA�]�������������܂��B �@�u���̉�c�́A�͂����肨���ă}���l�����Ɋׂ��Ă��܂��B�o�Ȃ���Ă�����X�̊�����Ă���ƁA����Ȃ���A�ǂ������C���Ȃ��B���������A�ߑO���̖������ł̌��莖���̓`�B�A�����āA�O���̊e����̕����ďI���B����������ɍ�点�����������̎�����ǂݏグ�āA����ł����܂��ł��B���ɉ����c�_���s����킯�ł͂Ȃ����A�������킳���킯���Ȃ��B�͂Ȃ͂����C�̂Ȃ���c�ł��B�܂��A�F���g�Ŏ����������ꂽ��ǂ��ł����B�l�̍�������������ł͏\���������ł��܂����B�v �@�]�������̂��̔����́A�������ɐ�y�i�̕����A���̋@���˂��ɂ͍ς܂Ȃ������Ƃ����킯�ł��B �@�u�ʂɕ����ɍ�点�����������āA���̖����Ȃ����낤�B����������āA��X�͑及�������畨���f���������B���ꂪ�����̎d�����B�v �@�u�܂��A�N�͏A�C�����Ă̕���������A��X���͌��C�����邩������Ȃ��˂��B�ł��A���͍��̕�����ʼn��̕s�����Ȃ���B�v �@�u�����Č��킹�ĖႢ�܂����A�F����̕��Ă��Ă��A���ɂ͊F���������镔�傪�A���ǂ�ȏɂ���̂��A�����Ƃ��킩��܂���B�܂�A�ǂ�ȉۑ������Ă��āA����ɑΏ����邽�߂ɁA�ǂ�Ȋ����Ɏ��g�����Ƃ��Ă���̂��A���邢�́A�ǂ�ȕ��j�Ŏd����i�߂Ă���̂��A���ꂪ�킩��Ȃ���ł���B�Ђ��ẮA���̉�Ђ����̐�ǂ��Ȃ�̂��A�傢�ɕs���ł��ˁB�v �@�u���������ɂ����܂��B�v �@�l���������������ɐ��߂āA�吺��グ���̂����}�ɂ������̂悤�ɁA�����ԕ������������X�ɑ����܂����B �@�u���ꂶ��N�́A���̉�c�͑S�����Ӗ��Ȃ��̂��ƌ����̂��ˁB�v �@�u��X���A����ł����ƌ����Ă���B�V���������ɏ��i�������畑���オ���Ă����Ȃ����B�����C�ɂȂ�Ȃ�B�������̌������́B�v �@�u�N�͕����ɂȂ肽�ĂŁA���̉�c�����Đ����o�Ȃ��Ă��Ȃ�����Ȃ����B����ʼn�����������Ă����B�ق��č����Ă��������B�v �@�������A�]�������͂����܂Ŗق����͂Ȃ������̂ł��B �@�u��X�͔N���҂���Ȃ���ł���B������Ⴄ����ɂ́A����Ȃ�̎d�������Ȃ����Ⴂ����ł��傤�B���̉�c�̂��߂̎��O���������āA�����ɂ�点����ł��傤�B���璲�ׂāA�����̓����g���āA�������܂Ƃ߂��킯����Ȃ��ł��傤�B�v �@�u�ȂƁB��X�������D�_���Ƃ����̂��B�M�l�́B�v �@�u�܂��A�܂��B�v �@����Ăċc�����̐ꖱ���Ȃ��߂ɓ���܂����B �@�u��������I�ɂȂ�Ȃ��ł���B�Ƃ���Ŗ]���N�B��ĂƂ����͉̂������B�N�͂��̕�������ǂ����������B�v �@�u���́A�e����ō��A�����e�[�}�ɁA�ǂ�Ȋ������Ȃ���Ă���̂��A�����m�肽����ł��B�������������Ă�����ł́A���ꂪ������܂���ˁB�Ⴆ�A�c�ƕ��ł͍���c�̂�ʔ�������v���W�F�N�g�Ɏ��g��ł��܂����A�����炭�݂Ȃ���́A�ڂ����m��܂��܂��B������Љ��@�����A���낢��Ƃ݂Ȃ���̈ӌ��������邵�A������Q�l�ɂ����������ʂ��オ�邩������Ȃ��B�݂Ȃ���̕����ł��A��X�̎��g�݂����邱�Ƃ��ł����Ȃ��ł����B�v �@�u���ꂶ�Ⴀ�A�N�͉�X�������̕����ʼn������ɂȂ��Ă���̂����������Ă��Ȃ��Ƃ����̂��ˁB��X�\���ƁB�v �@�u�����͌����Ă��܂����B���̕�����ł́A���̕����łǂ�Ȋ������s���Ă���̂����A�O����ł͕�����Ȃ��ƌ����Ă����ł��B���̉�c������������A���̂���ӌ��������ł���A������Q�l�Ɋe��������芈�������邱�Ƃ��ł����Ȃ��ł����B�v �@�u�������A�N�˂��B�v �@�u�܂��A������Ƒ҂��Ă����B���������̒�Ă��������Ă݂Ȃ����B�m���ɂ��̒���c���}���l���̌X���ɂ������B�����h���ɂȂ邩������Ȃ���B�Ȃ��ʔ���������Ȃ����B�v �@�u�������A�ꖱ�c�c�c�v �@�u�܂���������B����Ă݂悤�B�e���傪���A�ł��͂����Ď��g��ł��邱�Ƃ͉����A�V�������g�݂͂ǂ�Ȃ��̂��B����𗈌����甭�\���邱�Ƃɂ��悤�B�v �@�u���̏������A�݂Ȃ������ŁB�v �@���������A�]���������������݂܂����B �@�u�������A�������B���̕ɑ��āA���^�����A�ӌ���������邩��A�݂�Ȃ����ƒ��ׂė��Ă����B�܂��́A�l�������Ə��i�J������������Ă���B�v �@�u�������B�v �@�u�܂��A��������A��������B�v �@�������Đꖱ�����C�ɂȂ������߁A���̏�͉��Ƃ������܂�܂����B���ꂪ�A�O��̕�����ł̏o�����������̂ł��B �@�����āA�����̕�����̓��ƂȂ�\�\�\�\ �@�u���ꂶ�Ⴀ�A�܂��l�������̕�����n�߂悤���B�v �@�ꖱ�ɑ�����āA�l�������������オ��܂����B �@�u���̕��n�߂�O�ɁA�܂��A�]���N�Ɍ����Ă����������Ƃ�����B�O��̉�c�ł͌N�̒�Ăɔ��������ǁA���͍���A���̉�c�ŕ��邽�߂̎��O�����������ł���Ă݂āA�ǂ������Ǝv���Ă����B���肪�Ƃ��B�v �@�u�ق��A�ǂ����������B�v �@�u�����A�ꖱ�B�Ƃ����̂��A���̏�ŃE�`�̕��̏���āA���ƂŎ�������肷��킯�ł�����A���܂łǂ���ɕ����Ɏ�������点�čς܂��킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B�����Ŏ��O���������邽�߂ɁA�����Ō���̐����āA�����̖ڂł��낢�뒲�ׂĂ݂���ł��B�Ƃ��낪�A�����Œ��ׂĂ݂�Ǝv��ʔ����������ł���B����͂��ꂩ�甭�\���܂����A���܂ł̂悤�ɒP�ɐ�������ׂ������̕ł͂���܂���B���܂ŕ���������Ă��邾���ł͋C�t���Ȃ����������̖��_�Ƃ��A�ۑ�Ƃ��A�悭������悤�ɂȂ�܂����B�v �@�u�����A�悩��������Ȃ����B�v �@�u���ꂾ������Ȃ��ł��ˁB����ɓ�����Ă����̂́A���܂ł̎��̎d���Ƃ͈Ⴄ���̂ł����A�����Ă݂�ΐV�����d�������������Ă������Ƃł�����A�������g�̖����̎d���̂������ς��܂�����B���Ԃ̎g�����Ƃ��A�����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̎����Ƃ��A���낢��ƍH�v����K�v�������ł��B����ŁA������Z���t�}�l�W�����g�Ƃ����̂̑�����������܂����ˁB�v �@�u����Ȃɕς����̂��ˁH�v �@�u�����ς��܂���B�w�����A��������Ă���x�ōς��̂��A�����Ŏ葫���g��Ȃ���Ȃ�܂���ˁB�����A�֎q�ɍ����Ďw�����邾���Ƃ́A�d���̂������ς��܂���B�ŏ��́A�����Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������ł���˘f���܂�����B���܂ł́w�������Ă���x�����ōς�ł���ł�����B�����Œ�ĂȂ�ł����A�Z���t�}�l�W�����g���C����Ђœ������邱�Ƃ�����������ǂ��ł��傤�B�v
|
||||||||||||||||||||||||
| 12�@�˔��̉�c���s�� | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�͂��c�c�A�͂��c�c�A�����A�킩��܂����B�Ȃ�ׂ������A�p�ӂ��܂��B�͂��c�c�A���炵�܂��B�v �@��b���u���ƁA�ے��͂��ߑ����ЂƂR�炵�āA�c�Ɖۂ̃f�X�N�ɋ����ԕ����̊�����n���܂����B �@�u�݂�ȕ����Ă���B���ꂩ��}篁A��c����邱�ƂɂȂ����B�����ɉ�c���ɏW�����Ă���B�v �@���������ĉے��͐Ȃ𗧂��A�����𑣂��悤�ɉ�c���̕��֕����čs���܂��B�ˑR�̉�c�ɕ��C���̎Ј����A�d���Ȃ��Ȃ𗧂��܂��B �@�u�\��O�̉�c�Ȃ�āA���̖Z�����Ƃ��ɂ��܂��Ȃ��B�v �@�u�Ȃ��Ă����낤�B�v �@�u����Ȃ��ƂȂ�A�Ƃ��ƂƉc�Ƃɏo���܂��悩������B�v �����킹���Ј��������A���X�ɕs�������炵�Ȃ�����W�܂�ƁA�ے��͑�����c���n�߂܂����B�u���́A������A�В�����v�]�������ĂȁB�厊�}�A���ia�ɂ��Ẵf�[�^���W�߂Ȃ���Ȃ��̂��B�v �@�u�ǂ����Ăł����H�v �@�Ј��̂ЂƂ肪�q�˂܂��B �@�u�����A���ia�ɂ��āA�L�Ҏ�ނ�����������B�����ŁA���}�ɏ��ia�̃f�[�^���������A���̂��Ƃł��낢�뎿����������A�Ƃ������Ƃ��B�������ɁA������Ȃ�ׂ������~�����Ƃ����̂��В��̈ӌ�����B�v �@�u�����͌����Ă��A���ia�̒S����A�N�ł���B�ނ́A���c�Ƃɏo�Ă邩��c�c�v �@�u����͏��m���Ă����B�v �@�u�ǂ������ł����B�v �@�u�����ŕ������A�N�������������ɏo����f�[�^�͉�������H�v �@���������āA�W�܂��Ă����Ј������́A����X���Ȃ���l������ł��܂��܂������A�₪�ĉ��l���������܂����B �@�u�܂��A�N�Ԃ̔���͏o���܂��ˁB���N�̔���ƌ��ʂ��A���N�Ƃ̔�r�A�������N�̐L�ї��Ƃ��c�c�v �@�u���ꂩ��A���C���ڋq�w�Ƃ��̊ȒP�ȃ}�[�P�b�g�f�[�^���v �@�u���\���ɂ��ẮA�p���t���b�g������܂��ˁB�v �@�u����܂ł̃g���u���̎����A���q����̕]���̐��A�Ƃ��������̂͂ǂ������B�v �@�ے����₤�ƁA�ЂƂ�̎Ј��������܂��B �@�u����́A�l��͎����Ă��܂���ˁBA�N���߂�̂�҂��A���邢�͐�������ɒN���������ɍs�����c�c�v �@�u�ے��B����ς�A�N�ɗ\����L�����Z�����Ă�����āA�Ăі߂�����ǂ��ł����B�v �@�u����A����̓}�Y�C��B�厖�ȗ\����L�����Z��������A��X�̖{���ł���c�Ƃ����낻���ɂ��Ă܂ŁA�f�[�^�W�߂�D�悳����͎̂В����]�܂Ȃ����낤�B�v �@�u�������A��X�����̌�c�Ƃ�����܂����A�����������Ԃ͎��Ȃ��Ɓc�c�v �@�ЂƂ�̎Ј������������ƁA���̉��l�������Ȃ����ē����܂��B �@�u�킩�����B���ꂶ�Ⴀ�A�������悤�B�v �@�ے��͂��������ė����オ��ƁA����ɑ����܂��B �@�u�N�����̍l���Ă��邱�Ƃ͂킩���B�����ł����O���ŖZ�����̂ɁA���̂����˔��̉�c���A�f�[�^�W�߂Ŏ��Ԃ������ꂽ���Ȃ��A�Ƃ����̂��낤�B������A���̉�c�͒Z���ԂŏI����B�������Ȃ��c�c�A����10�����B����܂ł͕t�������Ă���B����Ȃ炢�����낤�B�v �@�ꓯ�̏��������t����ƁA�ے��͂܂���c��i�߂܂��B �@�u���̂���2���ԁA���Ƃ����Ԃ�����҂́H�v �@�ЂƂ�̎Ј�����������܂����B �@�u���ꂶ�Ⴀ�A1���Ԃ����Ȃ����A�Ƃ����҂́H�v �@���x��2�l����������܂����B �@�u�悵�A���ꂶ�Ⴀ�A�N�͂���܂ł̃g���u���̏ł�ׂĂ���B�ǂ������������āA�ǂ������������ׂ�B�v �@�ŏ��Ɏ���������Ј��ɂ����w��������ƁA���ɑ��̎Ј��ɂ��w����^���܂��B �@�u�N�́A�N�Ԕ���̐��ڂ��A4�N�O�̔������ɂ܂ş���Ē��ׂĂ����B�O���t�Ɛ����Ɨ����ŏo���Ă����B���ꂩ��N�́A���\���ɂ��āA�p���t���b�g�̕\���ɂ���ُ�̂��Ƃ��A��������Ńq�A�����O���ā\�\�\�\�\ �@�������āA���������3�l�̎Ј��ɁA���X�Ɩ����S���Ă��܂��܂����B���̍�Ƃ��I���ƁA�����S���ꂽ�Ј����q�˂܂����B �@�u���ʕ͂ǂ����܂����B�܂��W�܂�܂����B�v �@�u����A���̕K�v�͂Ȃ��B�e���̍�Ƃ̐i���m�F��A���ʂ̎��܂Ƃ߂Ƃ������A���_�[�t�H���[�͖l���ʂɂ�邩��A�݂�ȂŏW�܂�K�v�͂Ȃ��B����Ȃ��c�̂��߂ɗ]���Ȏ��Ԃ������邱�Ƃ��Ȃ����A�݂�Ȃ̋M�d�Ȏ��Ԃ��₳���ɑΏ��ł��邾�낤�B�v �@�u���ꂶ�Ⴀ�AA�N�́H�v �@�Ј��������ƁA�ے��͓����܂����B �@�u�ނɂ͉c�Ƃ���߂��Ă���Ή����Ă��炨���B�ނ��A�邱�Ƃɂ́A�В����f�[�^�ɖڂ�ʂ��āA�������₪���邾�낤����B���̎҂ɂ��A������Ŏ肪�Ă���悤���Ɣ��f������A���̎��͉�����`���Ă��炤���������A���̂���ł��Ă������B�ȏ�ʼn�c�͏I��肾�B�v
|
||||||||||||||||||||||||
| 13�@��ʐ����̉�c | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�����́A�ǂ�Ȓ��q�����v �@���������Ȃ����c���ɓ����ė����]�������́A�c�Ɖے��ƋƖ��ے���2�l�̕������A�݂����ɂݍ����č��荞��ł����ʂɏo���킵�܂����B �@�u�܂��A�ɂݍ������B���ꂶ�።���B�N�����ɁA�o��Z�̂�����V�����H�v���Ă����悤���͔̂��N�O����B����͉c�ƕ��ɂƂ��āA��̉�c�v���W�F�N�g�Ɠ������炢�d�v�ȃe�[�}�ȂB�E�`�̕����ɁA���Ƃ����ȏ�ɂ��q����Ɖ�����𑽂������Ă��炤���߂ɁA�d���̂��������낢�댩�����Ă����B����͂��̈���B���̓_����2�l�͂�����ƔF��������̂��B�v �@�b�����Ă��邤���ɁA�����̌���������ƌ����Ă���悤�ł��B �@�u���������A�������ȂI�I�v �@�u���Z�`�[���A�c�ƂƋƖ��̂ǂ���ŋN�[���邩�Ƃ����_�Łc�c�v �@�c�Ɖے�����������ƁA����ɑ����ċƖ��ے��������܂��B �@�u���ł͌o��̐��Z�����A���Z�̓`�[�̋N�[���c�Ƃł���Ă����ł��傤�B���������́A�N�[�͋Ɩ��ł���Ă�����āA���̈�_����Ȃ�ł���A�c�Ɖے��́B�Ƃ�ł��Ȃ��b�ł��B������͐l��s���Ȃ�ł�����A����ȏ�̎d���͈������܂���B�v �@�u�����������ǂˁA�l��s���͂�������������B��ʔ��牽���A�o��̐��Z�ɔ�₷���Ԃ����ăo�J�ɂȂ�Ȃ��B���ꂪ�y�ɂȂ镪�A�c�Ƃɏ[�Ă鎞�Ԃ������Ȃ�B�v �@�u�l��Ȃ�c�Ƃ̕����܂��}�V���낤�B�܂��A�������ōH�v����̂����Ă��B�v �@�u�܂��A�҂āB�v �@�]����������ނȂ�2�l�̌����������~�߂ɓ���܂��B �@�u�N�����́A���N�̊ԁA�����Ƃ���Ȃӂ��Ɍ��������𑱂��Ă����̂��H�v �@�u�����A�܂��B�v �@�u���ꂶ�Ⴀ���_���o�Ȃ����낤�B�v �@�u�����A�w���_�͎���Ɏ����z�����ȁx���Ă��ƂɂȂ�܂��ˁB�v �@�u�Ȃ�܂��ˁA�Ȃ�Č����Ă���ꍇ����Ȃ����낤�I�d���̌䉟���t�����������肵�Ă��Ȃ��ŁA�����͖��̖{�����l���Ă݂���ǂ����B�N�����͂����Ƃ��������Ă��Ȃ��悤���B�o��Z�̕��@��ς���Ƃ������ƂɁA�ǂ�ȈӖ�������Ǝv���B���̖��̖{���͉����H�l��̂���A�Ȃ������Ȃ̂��H�v �@�u�����A�����ł��傤�B�v �@�c�Ɖے��������܂��B �@�u�N�͂ǂ��v���H�v �@�u�����l��̖�肾�Ǝv���܂��B�v �@�u�o�J�����B�l��s���͍��Ɏn�܂������Ƃ���Ȃ��B�������̖{�����Ȃ�Ă�����Ȃ��B�v �@�u�������B�����B�v �@�u��������A�I���̎���ɓ����Ă݂�B�E�`�̕��͉c�Ƃ����B�܂��X�̎d���́A�����ăi���{�̎d�������Ă��Ƃ��B�����ʼnc�Ɖے��ɕ������A���̃i���{�Ƃ����̂́A�ǂ��������Ƃ��B�v �@�u����́c�c�A���ォ�珔�o������������Ďc�闘�v�̂��Ƃ��A�܂�̓i���{�Ƃ������Ƃł��B�������A���̗��o�ƁA���Z�`�[�̋N�[���ǂ��炩�����Ƃ����b�Ƃ́A�W�Ȃ����Ƃł��傤�B�v �@�u�傢�ɊW�����B�ǂ����w�o��Z�͖�����邱�Ƃł͂Ȃ��A�����̌��Z�ɊԂɍ��킹������x�Ȃ�čl���Ă���낤�B�����̊ԍۂɂȂ��āA�݂�Ȃ͂��������ɂ�邭�炢������A�����̐��Z�Ȃ�Ė������Ƃ����킯���ȁB���Ƃ���A�E�`�̕��������A�i���{�҂��ł���̂��A�v�Z�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����������A�E�`�̕��������ǂ̒��x�̐��ʂ������Ă���̂��A�܂������c���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ȁB�v �@�u�����������ƂɂȂ�܂��B�v �@�u�܂�A�o��Z�̕��@���H�v�ł��Ȃ���A�N��2��A����Ɖ����̂��܂ɂ����A�E�`�̕��̎d���Ԃ���c���ł��Ȃ��킯���B����ł́A�{���̈Ӗ��ł̃}�l�W�����g���ł������Ȃ����낤�B�v �@�u���������Ƃ���ł��B�v �@�u���߂Ė����A�����ăi���{�̐��ʂ��킩��悤�łȂ��ƁA������Ƃ����c�Ɛ헪�����Ă���킯���Ȃ��B�c�Ɛ헪�����Ă��Ȃ���A�����ɉc�Ɛ��т��グ���Ȃ�����Ȃ����B�������o��Z�A���������d������Ȃ��Ǝv���ăo�J�ɂ��Ă邩��A���݂��ɓ`�[���ǂ����邩�A�����t���������Ƃ����l�����Ȃ���B�R�g�́A�E�`�m���������Ԃ����ނ��́A�d�v�Ȗ��ȂB�����������_�ŁA�����P�x�l���Ă݂Ă���Ȃ����B�v �@���������c���āA�]�������͉�c�����o�čs���܂����B�c���ꂽ�Q�l�́A�܂����˂����킹�Ęb���������n�߂܂����B �@�u�����̌����Ƃ���A�c�ƕ��̕����ɂ�������肾�ȁB�ǂ������Ȃ�A�����Ƃ��킸�A�������Z���������ǂ����B�v �@�u�����������A������ƌo��Z�������Ă����̂��A�ʓ|����B����łȂ��Ƃ��O���͖����A�c�Ɠ���������Ȃ����Ⴂ���Ȃ����B���̂����o��Z�ƂȂ�Ɓc�c�v �@�u����Ȃ����ɁA�g�����o����������ޗ��������Đ��Z���ꏏ�ɂ������ǂ����B�v �@�u�����l�����B�������A�o����L�����邾���ł́A�����ɂ͂Ȃ�B�`�[�͂ǂ�����H�v �@�u�ŋ߂̃R���s���[�^�E�\�t�g�ɂ͌o��Z�̃\�t�g������炵���B�v �@�u�Ȃ�قǁB����ƌo��Z�����˂��\�t�g������āA��p�̒[���Ŋe���A�f�[�^��ł����߂A���Ƃ̓��C���R���s���[�^�������I�ɓ`�[������Ă����Ƃ����킯���B����Ȃ�A�o����Ԃ��Ȃ���ȁB�v �@��������30�������������Ƃɂ́A���Ƃ��b���������I���A2�l�����Ė]�������̂��ƂɌ���܂����B2�l�̕��āA�]�����������������ł��B �@�u2�l�Ƃ��A�������P�ɂȂ������낤�B�����̓y�U�����ōl���Ă��Ă͉����ł��Ȃ����Ƃ��A�����Ƒ傫�ȓy�U�ɏ���āA�傫�Ȏ��_�ōl�������Ă݂�ƁA���\������������̂���B�v
|
||||||||||||||||||||||||
| 14�@���i�J���E���̉�c | ||||||||||||||||||||||||
| �@�u�Ƃ����킯�ŁA����܂ʼnc�ƂƊJ���Ƃŏ��������d�˂Ă������ʂƂ��āA�S�ق�̊J���̂��߂̃v���W�F�N�g���Ă��܂��B�������̂��l���́H�v �@���̂Ƃ��̉�c���ł́A�J���ۂƉc�Ɖۂ̍����ŁA�V���i�J���̂��߂̃v���W�F�N�g��c���J����A�J�������Ɩ]���c�ƕ������Ƃ��ǂ�������Ă��܂����B �@�u������Ȃ��B�v �@�J�������������������̂��A�]���������傫�����Ȃ����܂����B �@�u�Ƃ���ŁA���̃v���W�F�N�g�͂ǂ�ȃ����o�[�ł����B�v �@�u����܂ł̒���I�ȏ������̌��ʂ����̃v���W�F�N�g�ł�����A�����o�[�͍��܂łǂ���A�������������Ă����l�ԂłƎv���Ă܂��B�v �@�u�Ƃ����ƁA�S���ʼn��l���B�v �@�u�c�ƁA�J���Ƃ�10�l���ŁA���v20�l�ł��B�v �@�u����́A������ƍl�����̂��ȁB�v �@�]���������a���������Ă��������ƁA����ɊJ���������q�˂܂����B �@�u�ǂ����Ă����������ƂɂȂ���B�l�I�͂ǂ�������Ō��߂��B�v �@�����o�[���\���āA�ЂƂ�̎Ј��������܂����B �@�u���܂ňꏏ�ɂ���Ă��܂������A���ꂩ����C�S�̒m�ꂽ�A���ł��̂������Ǝv�������̂ł�����B����Ƃ����̃����o�[�ŁB�v �@�u����A����͂܂�����B�ǂ��������i�����̂��A��{�I�ȕ������͂������܂��Ă���킯���낤�B����ɂ��܂��}�b�`�����l�I�Ȃ炢�����A�P�ɍ��܂ł̉���������Ƃ������R�����Ȃ�A�^���ł��Ȃ��ȁB�v �@�u���̈ӌ����J�������Ɠ�������B�`�[�����[�N��厖�ɂ��������Ă����N�����̋C�����͂킩�邯�ǁA���������������l�I�̎d���͈Ⴄ���낤�B�v �@�u�Ƃ��������ƁA�ǂ������l�I���B�v �@�����o�[�̑�\�҂͌˘f���Ȃ�����J�������ɐq�˂܂����B �@�u�����������^�̎d���́A�K�C�҂͒N���Ƃ����̂��L�[���[�h�ɂȂ�B���ɏ��i�J���ƂȂ�ƁA�v���W�F�N�g�����ɐi�߂Ă����ɂ́A����o���̐��I�m�����K�v�ƂȂ�͂����B20�l�������o�[�����ẮA�����ɂ͕K�v�Ȓm�����o�����Ȃ��A�}�`���A���A���\�����Ȃ����B�v �@�u�J�������̌����Ƃ��肾��B���̂��߂ɂ́A���������o��������̂�������������Ȃ��B�������A���܂�ɃA�}�`���A������������ł́A���ǂ��납�A�ӌ����܂Ƃ܂炸�ɁA�v���W�F�N�g���̂��̂������Ƃ��i�܂Ȃ��A�Ȃ�Ă������Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ���B�N�̐��m�����K�v�Ȃ̂��A�N�̌o���������炢���̂��A������l���āA������x�A�l�I����蒼��������������B�v �@�u�l�������炷�Ƃ��������ōl���Ă݂���ǂ����ȁB�v���W�F�N�g���{�i�I�ɓ����o���悤�ɂȂ�����A�l�������ꑊ���ɕK�v���낤���ǁA���̒i�K�ł͏��l���̕��������₷�����낤�B�v �@2�l�̕����ɂ�����Ĕ����ꂽ�̂ł́A��蒼����������܂���B��1��ڂ̃v���[���e�[�V�����́A�������ċp������Ă��܂��܂����B�����āA1�T�Ԍ�̍����A��2��ڂ̃v���[���e�[�V�������A������c���ōs���Ă���̂ł��B�O��Ɠ��l�ɁA��\�Ј���2�l�̕�����ɁA����������Ă��܂��B �@�u���ӂ���̕����̂��������Ƃ���ł����B���ꂩ��"�K�C�҂͒N��"�Ƃ����ϓ_�Ől�I�����Ă��邤���ɁA�V���i�̃R���Z�v�g�܂ŋ�̓I�ɂȂ�����ł��B�v �@�u�悩��������Ȃ����B����Ń����o�[�͂ǂ��Ȃ����B�v �u���茳�̊�揑�ɏ����Ă���Ƃ���A7�l�̃����o�[�ł�肽���Ǝv���Ă܂��B����̏��i�͉��i������܂��̂ŁA�܂��c�Ƃ���͍��z���i����Ɉ����Ă����l�ɁA���̃v���W�F�N�g�Ɏc���ĖႢ�����Ƃ������Ă܂��B�v �@�u�Ȃ�قƁA�Ȃ�قǁB�v �@�u�J������́A���Ƀf�U�C�������ӂȎ҂ɎQ�����Ă��炢�܂��B��͂荂�����̂���f�U�C�����H�v����K�v������܂��̂ŁB�v �@�u����A�������낤�ˁB�v �@�u�Ƃ���ŁAA�N�Ƃ����̂́A�V����������������o�[�̂悤���ˁB�v �@�u�����ł��B���̏��i�̓}�C�N���R���s���[�^���䂪�L�[�|�C���g�ɂȂ�܂�����A����Ƃ��}�C�R���̐��ƂɎQ�����Ă��炢�����Ǝv���āA���܂ł̏�������̃����o�[�ł͂Ȃ���ł����A�����������Ĉ��������Ă�����ł��B�v �@�u������Ȃ����B�v �@�u�x�X�g�̐l�I���Ǝv����B�m���ɌN�̌����Ƃ���A���i�̃R���Z�v�g���O���薾�m�ɂȂ��Ă�ˁB���������v���W�F�N�g���X�^�[�g�����悤�B�v
|
||||||||||||||||||||||||
Copy Right�@(���j�d���̉Ȋw������