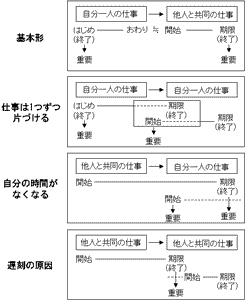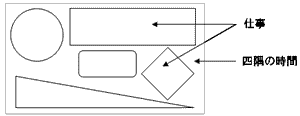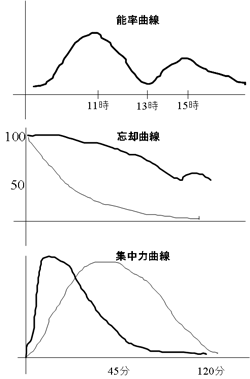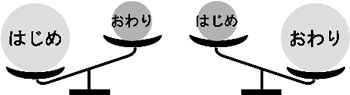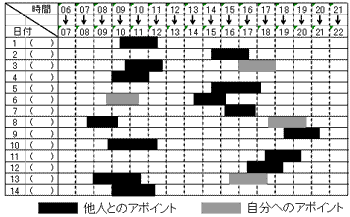| ■□■□ 第1時限 時間を創り出す ■□■□ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 「四つの時間」をまず知ろう 仕事と時間の関係は、どんな人でも「四つの時間」しかありません。 自分一人の仕事の「はじめ」と「終わり」、 他人と共同の仕事の「はじめ」と「終わり」―この四つの時間です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 最初に、この章では、時間のつくり方を考えることにします。 そのためには、まずある程度、仕事と時間の関係を知っておく必要があります。 今や書店に行くと、タイムマネジメントや仕事術の本が山ほど並んでいます。 とても全部読むことはできません。読んだからといって、時間がつくれたり、仕事の達人になったかというとその保証もありません。しかし、ご安心ください。 下図、これ一枚でタイムマネジメントのすべてを語る、といっても過言ではありません。この図一つで、時間もつくれますし、仕事の達人にもなれます。これを理解できれば、本書をはじめから終わりまで全部くまなく読まれなくても、本書の購入の目的はおおかた達成できます。 では、説明します。プロローグで「仕事のOS」と「仕事のスペクトル」についてお話しました。この図は、その二つをかけあわせて作ってあります。 仕事は、誰がやるかでみると、「自分一人」と「他人と共同」というのが「仕事のOS」です。また、仕事には、「開始(はじめ)」と「期限(終わり)」がある、というのが「仕事のスペクトル」です。 この二つの考え方から、仕事と時間の関係は、どんな人でも「四つの時間」しかないといえます。つまり、自分一人の仕事の「はじめ」と「終わり」。他人と共同の仕事の「はじめ」と「終わり」の四つです。この四つをしっかりコントロールできれば、時間もつくれますし、仕事の達人にもなれます。 ところで、みなさんは、この四つの時間のどれをコントロールしていますか? 四つを全部コントロールしているという人はほとんどいないと思います。逆に、他人と共同の「はじめ」に気をつけていない人も、ほとんどいないと思います。多くの人は、他人と共同の「はじめ」だけを一生懸命管理しています。 四つあるのに、一つだけの管理。これでは、時間もつくれませんし、達人にもなれません。 では、そうしたらいいのか? 一番いいのはすべての仕事の、四つの時間を管理することですが、そんなことは、多分不可能です。現在のスケジュール帳は、真っ黒になりますし、何より、疲れます。 そこれ、おすすめは、「自分一人」の「はじめ」と「他人と共同」の「終わり」の二つだけを気をつけるようにしてください。 自分一人の仕事で大事なものは、そのスタートをスケジュール帳に記入すること。それだけです。他人と共同の仕事は、「はじめ」を守るのはビジネスマナーとして当たり前、ワンランクアップを目指すなら、他人と共同の「終わり」です。 アポを取るときも、決められた時間どおりに始まらなくても、時間どおりに終わらせることです。 これだけ実践すれば、あなたの時間は増えること間違いなしです。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 07 「四隅の時間」を活かそう ある仕事が終わって次の仕事までアイドルタイムのことで、 別名「こま切れ時間」を指します。 仕事のできる人は、この「四隅の時間」をうまく活用することで生産性を上げています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 前節の四つの時間がメインディッシュなら、この節の「四隅の時間」(下図)は付け合せです。 美味しい料理も、付けあわせがまずいと台なしになりますし、メインディッシュがいただけなくても付け合わせが良くて、それだけをおかずに食事をする、ということはあるわけです。 さて、この「四隅の時間」は、別名「こま切れ時間」とも呼ばれています。 ある仕事が終わって次の仕事までのアイドルタイム(アイドリングタイム=エネルギー充電時間、息抜き=決して手抜きではありません)のことです。 一日の中で必ず生じて来ます。 あたかも、トランクに物を詰め込むと、隙間があくようなので、「四隅の時間」と、タイムマネジメント業界では、呼ぶことがあります。 私の顧問先の社長さんや部長さんでも、結構この時間を活用している人は多いです。そして、この時間を活用している人で、仕事のできない人もいない、というのも事実です。 当然「四隅の時間」は、こま切れ時間ですから、大きな仕事、難しい仕事はできません。 しかし、仕事には、結構、雑事やすぐ終わるようなものもあります。これらをやらずに貯めておくと、大仕事になってしまいます。 仕事のできる人は、この「四隅の時間」の活用で、ささいな仕事が大仕事にならないよう、コントロールしているといえます。 私の知人で、株式会社武蔵野(東京都小金井市)の小山昇社長は、この「四隅の時間」活用の天才ともいえる人です。 彼は、移動時に歩く時間まで、「四隅の時間」として活用しています。 例えば歩きながら、社長連絡用のボイスメール(Eメールの音声版)で社員からの報告を聞いたり、指示を出したりしています。時によっては、ボイスメールで決裁をすることもままあります。 また、もう一つ紹介すると、電車や乗り物に乗ると彼は、カバンからFAXを取り出します。それは社員の方からの業務週報です。乗車中(座れた場合のみ)という「四隅の時間」で日報、週報のチェックを行います。 ここまで行けば、もういうことはありません。 ここまで、「四隅の時間」を活用すると、さぞかし、「四隅の時間」も幸せだと感じているのではないでしょうか・ちなみに小山社長の会社は、この不況の中、毎年、増収増益です。 そこまでしなくても、デスクワークの最中に、ささいな仕事リストを作成しておいて「あ、四隅の時間だ」と思ったら、それをやる体制だけは整えておきたいものです。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 08 時間と脳に関する三つのデータ 時間とうまく付き合うためにも、脳みその一般的傾向を知りましょう。 一日中で脳が最も元気に働いてくれる時間は? 脳はどれだけ覚えていられるか?脳がガンバレる持続時間は? |
|||||||||||||||||||||||||||
| ここでちょっと息抜きです。 時間とうまく付き合うためにいくつかのデータを紹介します。 仕事を進めるときの参考にしてください。 下図で紹介してあるのは三つです。<能率曲線><忘却曲線><集中力曲線>です。 すべて時間と私たちの脳みそとの関係を表したものです。 私たちは脳みそを活用して仕事をしています。仕事の最中に、そのことを意識している人は、まずいないと思いますが、意識するしないにかかわらず、すべては、脳みそ様のおかげです。 そこで、脳みそ様の一般的傾向を知っておいても損はないでしょう。 まずは、<能率曲線>から。 これは、一日の中で脳みそ様が元気に働いてくれる時間を表しています。睡眠のサイクルが偏っている人は、当てはまらないことがあります。健康な普通の人であれば、午前11時前後の数時間と、午後3時前後の数時間は、脳みそ様がよく働いてくれる時間です。逆に、午後1時前後の時間は、「おーい、働け!」といっても脳みそ様は「働くのイヤダ!」といって、お昼寝の時間ということになります。午後1時から大事な商談が恒例となっている人、成果出てますか?イマイチだったら、午後1時ははずしましょう。 次に、<忘却曲線>です。 これは、脳みそ様がどれだけ覚えていられるかという曲線です。通常は、一日も経つと半分以上忘れてしまうのが、健康で普通の人です。物覚えの良い人、記憶力の良い人も中にはいますが、そんな人は例外です。例外を相手にしても勝負になりません。しかし、私たちの脳みそ様は、結構使えます。学校の授業ではないですが、復習、これが大事です。できれば、覚えたすぐあとに振り返る(復習する)だけで、記憶に残る量は格段に違ってきます。私のセミナーでも、前に受講したのに、一年とか二年たってまた受講に来る人がいます。そんな人たちが、決まっていうのは、「あー、思い出した。もう忘れない」です。。脳みそ様はちゃんと働いてくれているわけです。 最後は、<集中力曲線>です。 これは、脳みそ様が、ガンバレる持続時間のことです。トレーニングジムで、エクササイズをやって、何時間も同じトレーニングは、普通できません。筋肉がヒメイをあげるわけです。それと同じです。筋肉も私たちの体の一部、脳みそ様も同じです。ガンバレる時間というのがあるわけです。一般的には45~60分です。これ以上同じことをやっていると、脳みそ様もヒメイをあげることになります。ただ、この曲線は、最近、一説によると15分ともいわれています。私の知人の大学教授が、15分間同じテーマで講義すると学生があきるといっておりました。小学校でも15分で、授業にならなくなる教室はたくさんあるようです。これから先の日本はどうなるのだと、ついつい心配になってしまいます。しかし、脳みそ様も体の一部、トレーニングで持続力がつきます。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 09 「時間のしくみ」で人を動かそう 人を動かすには、「四つの時間」のうち、「他人と共同の仕事の終わり」に注目しましょう。 これをうまく活用すると、人を容易に動かすことができるようになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「四つの時間」のことについては、前にお話しました。 タイムマネジメントの基本中の基本です。 この「四つの時間」を活用して、人を動かす方法をお伝えしましょう。 結論からいわせてもらいます。 「四つの時間」のうち、「他人と共同の終わり」。これを活用すると人を動かすことができます。 やり方は、簡単です。 まずは、相手からアポが入って、会いたい、打合せしたい、おじゃましたい等の電話、メールが入った場合の対処です。 この際のポイントは、面談の「はじめ」と、「終わりの時間」を必ず相手に伝えることです。 「10時から11時までの1時間ならOKです」という具合です。 これによって、少なからず相手に緊張感を与えることができます。 「貴重な時間をいただいた」と、まともな人なら感じるはずです。 これが大事です。 この緊張感があると、相手が遅刻することはまず減るはずです。さらには、いただいた時間が大事なものに思え、打合せの準備もしっかりしてくるでしょう。 面談はしたものの、会わなきゃよかった、と後で悔やむことは、ビジネスシーンで多々あるものです。これを防ぐことができます。 せっかく貴重な時間をそれもタダで提供して、無意味な時間では、やってられません。 しかし、面談の終わり時間を告げても、遅刻したり、準備なしにやってきて無意味な中味の人もいるのは事実です。 そういう人とは、一緒に仕事をしても、多分いいことはありませんから、付き合うべき人かどうかのチェックにも、このテクニックは使えます。 また、逆に、こっちからアポを入れる場合は、必ず「終わりの時間」を伝えてあげましょう。 ビジネスマナーとしても、実は当然ですが、これをやれているのは、ごく少数な方だけです。ですから、かえって効果満点です。目立ちます。 「あいつは、他の連中とは違う」、と一目おかれることは、間違いなしです。 さらには、面談終了間際になると、先方から「時間はだいじょうぶ?」なんて、いってくれる可能性も大です。客先で長話に、付き合わされて、次の客先との面談が気になる営業マンも多いと思います。 一度、試してみてください。 今よりは、ちょっとはましになるはずです。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 「投下時間」の考え方を知ろう 投下時間とは、仕事は「はじめ」と「終わり」の間の時間のことです。 積極的、主体的に仕事をする簡単な方法は、 仕事の「はじめ」と「終わり」を自らコントロールすることです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| この節では、「仕事のスペクトル」の基本的な考え方である「投下時間」について、お話ししましょう。 投下時間とは、仕事の「はじめ」と「終わり」の間の時間であることは、誰にでもわかることです。 しかし、実際の仕事の現場において、この「はじめ」と「終わり」は、どれくらいはっきりしているでしょうか? 実は、あまりはっきりしていない、というのが実態ではないでしょうか? ある書類を作成する仕事があるとします。 あなたは、そのようにやっていますか? とりあえず、頃あいをみて、やる気になったら(実はやらざるをえなくなってから)、なんとなくはじめて、とりあえず仕上げるまでやる。そして、仕上がったときが終わり。 こんな状態の中で、あなたの主体性とか、積極性とかは、どこにあるんでしょうか? 仕事がつまらないとか、流されているようで不安だとか、多くの人は感じた経験があるはずです。 その原因が、仕事の「はじめ」と「終わり」のコントロールを破棄したことが原因で生じている、といったら、信じますか? 信じられる人は、もうだいじょうぶ。明日から投下時間のコントロールは格段に良くなります。 信じられない人。もうちょっと、この先を読んでください。 「とにかくやる」と思って仕事をやる人と、「30分で仕上げる」と思ってやる人との違いを考えてみましょう。 前者は、過去の経験(たいした経験ではないかもしれない)を頼りに、思いつくまま、手あたりしだいに仕事を進めるということになるでしょう。このスタイルについては本人は、主体的で積極的だと思っているかもしれません。 後者は、時間どおりに終わらせるには、どうしたらよいか、まず考えて取り組むはずですし、スタートラインから、終わりの時間にむかって意識も集中しています。脳みそ様の回転も随分と違うはずです。(チャンスがあったら、科学的に調査をしたいものです)。 自分の持てる力を駆使して、また切り拓いての仕事ですから、楽しいし、力のつきます。 差は、3ヶ月もすれば、目に見えて分かるほどになります。 積極的、主体的に仕事をすれば、間違いなく力はつきます。成長します。 それを実現するための、簡単な方法として、仕事の「はじめ」と「終わり」を自らコントロールすることをおすすめします。そうすれば、自分に残された投下時間である「時間予算」をはあくできるため、より主体的、積極的に仕事ができます。(下図参照)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 「投下時間の基本的性格」とは? おしりに火がつくまで手をつけない人は、考えたくない人です。 自分の残りの「投下時間」がどれだけあるか(時間予算)を 見極めることは「時間力」をつける最初の一歩です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 前の節で、「投下時間」という考え方と、その考え方が私たちの仕事のスキルアップに寄与している、と話しました。 この節では、もう少し詳しく、「投下時間」について考えてみます。 「投下時間」という視点で私たちの仕事をのぞけば、人間の性(さが)が垣間見えます。 下図のように、「投下時間」が多くても、少なくても、なかなか主体的、積極的に事をはこべないのが人間の本質のようです。 「投下時間」が少ない状況を一言でいえば、期限が迫った状態です。別名、おしりに火がついた状態ともいいます。 多くの人は、この状況にならないと、重い腰(おしり)を動かしません。火がついた状態で熱いでしょうから、動き回って消火活動に入るわけです。 でも、どうして、いつも同じことを繰り返すの?という素朴な疑問が残ります。 答えは簡単です。いつも消火活動ばかりで、考えることにエネルギーを回せないからです。 この考えることにエネルギーを回せない、というのはとってもまずいことです。 じゃあ、消火活動中は、考えているのか?という次なる問題が生じます。 これも答えは簡単です。 考えていません。 というよりは、考える必要がありません。投下時間が少なくなればなるほど、選択の余地は少なくなるというのが、真理です。選択をする、道を選ぶ、方法を選ぶということは、考えることです。選択の余地がないということは、考える必要がないということです。 おしりに火がつくまで手をつけない人は、別名、考えたくない人ともいえます。 とはいっても、おしりに火がつくと何かしらの事は処理するわけで、ちょっとは物事は前進しますが、たちの悪いのは、たっぷりと投下時間があるときです。 これはさっきの逆で、選択の余地は、山ほどあることになりますが、考えることを忘れてしまった人にとっては、苦痛以外のなにものでもありません。 こういう人は、とりあえずどうするかというと、フタをします。フタをして、見なかったことにします。つまり、その仕事をしない、ということになります。 この「投下時間」と、私たちの性が、仕事に追い回される状況をつくっているといっても過言ではありません。 対策は一つです。 実は、投下時間があるようで(あると思えば、ゆとりをかましてしまいます)、ないという現実をしっかり見つめることです。自分の残りの「投下時間」がどれだけあるか(時間予算)を見極めることは、タイムマネジメント、時間力をつける最初の一歩ということになります。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 「時間のつくり方」のヒミツを知ろう ポイントは「時間管理」ではなく、「仕事の管理」です。 時間を使って行なう仕事―「四つの時間」「四隅の時間」「時間予算」「自分一人のはじめ」― に着目することが、時間をつくるコツです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| さて、いよいよ本章のテーマの「時間のつくり方」です。 が、しかし、その前に、「タイムマネジメント」という単語の説明をちょっとさせていただきます。 「タイムマネジメント」は、「時間管理」だと思っている方、即刻その考え方を捨ててください。考えたこともない方、じっくり読んでください。 「タイムマネジメント」は、確かに直訳すると「時間管理」ですが、この言葉は、もともと、論理的に「破綻(はたん)」をきたした言葉です。そのせいか、まず辞書には載っていません。 明日の10時にお客様のクレームが入るとか、今日は一日30時間にするとかができれば、確かに時間をコントロールしているわけですから、「時間管理」と訳してもよいし、「タイムマネジメント」といってもよいでしょう。しかし、それができる人は、一人もいません。不可能です。 本当は、「時間管理」ではなく、「仕事の管理」なのです。 「タイムマネジメント」ではなく「タスクマネジメント」が正しい言葉の使い方だと思っています。 そのことを理解したうえで、もう一度、「時間をつくる!?」を考えると、答えは簡単、「無理だぁ!!」ということです。 しかし、時間はつくれなくても、上手に使うことはできます。 そのためには、ある程度の準備が必要です。 そうです。時間ではなく、時間を使って行なう仕事に着目することが、時間を上手に使う準備作業ということになります。 その具体策は、下図にあげた次の四つということになります。 ①まずは、「四つの時間」を知る。特に、「自分一人の仕事のはじめ」と「他人と共同の終わり」です。「他人と共同の 終わり」は前にある程度説明しました。「自分一人のはじめ」については、次の章で詳しく説明します。 ②次に、「四隅の時間」、今まで活用されていなかった時間を活用する、ということですから、時間をつくるということ になるかもしれません。 ③さらには、自分が投下できる時間を知る。つまり、「時間予算」を知ることです。予算が足りなかったら、まず、仕 事を捨てましょう。やらないということです。これは、まったくやらないというのと、人に任せるということの二つの選択肢があります。後者はあとの章で説明します。 ④そして、最後に一番大事なことは、「自分一人のはじめ」、次の章でも説明しますが、まずは、すれをスケジュー ル帳に記入するだけでも、成果は出ます。だまされたと思ってやってみてください。いろいろな効果が出てくるはずです。
|
|||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) The Association of Japan Time Management Popularization. All Rights Reserved.